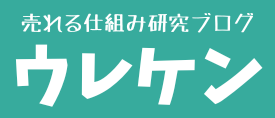「正しい経営判断を下すにはどうすればいいか…」
「いろんな人の利害関係を考えすぎて、なかなか決断できない…」
「大きな決断を下す際、いつも守りに入ってしまう…」
そんな悩みを抱えていらっしゃる社長様や経営者、管理職のみなさまに、今回は、
- 決断できない経営者が身につけるべき2つの考え方
- 経営者が正しい判断を下すために必要なこと
をご紹介いたします。
経営者の仕事は「決断すること」といっても過言ではありません。
- 商品やサービスの価格を値上げ(または値下げ)するかどうか?
- 送料を無料(または有料)にするかどうか?
- 大きな取引先と契約する(または契約を解消する)かどうか?
- 新しい事業をスタートするかどうか?
など、会社の運営していると次から次に決断を下す場面が出てきます。
特に、会社の将来を左右するほどの決断や、その後の業績を大きく左右する決断は、そう簡単にできるものではありあません。
今回ご紹介する考え方は、日頃から「なかなか決断できない」という社長や管理職の方をはじめ、経営者が大きな経営判断を迫られた時に役立つ、シンプルかつ有効な考え方です。
それでは早速みていきましょう。
決断できない経営者が身につけるべき考え方
決断できない経営者が身につけるべき2つの考え方、それは
決断を下す前は「戦略的楽観主義」、決断を下した後は「防衛的悲観主義」
という考え方です。
「戦略的楽観主義」とは
最高の結果を予測して、冷静さを保ちながら目標を高く設定する方が良いとする主張です。
「防衛的悲観主義」とは
最悪の結果を想定して、起こりうるあらゆる悪い事態を予測する方が良いとする主張です。
では、なぜ重要な決断を下すときは「戦略的楽観主義」で、
決断を下した後は「防衛的悲観主義」が良いのでしょうか?
例えば、新商品の価格を設定する場合、
「戦略的楽観主義」を主張する人は競合他社やお客様の許容範囲を計算に入れて「これくらいなら売れるだろう」と、利益率が最も良い価格帯で勝負します。
一方で、「防衛的悲観主義」を主張する人は、利益率よりも「この価格であれば間違いなく売れるだろう」という確実性や安全性を重視した価格を設定します。
プライシング(価格設定)は、最も大きな利益が得られるように行うべきですから、
「防衛的悲観主義」よりも「戦略的楽観主義」の方が利益を最大化できることは明らかです。
しかし、いざ価格が設定されて販促プロモーションが始まると、考え方が逆転します。
「戦略的楽観主義」を主張する人は、
最高の結果から逆算した費用対効果を勘案して、広告宣伝や販促プロモーションに予算を投じます。
一方で、「防衛的悲観主義」を主張する人は、
最悪の事態を考えて、広告費や販促費は最小限に抑え、その費用対効果を検証しながら、より大きな効果が期待できると確信が持てるまで、慎重にプロモーション活動を進めます。
前者の広告宣伝が予想通り大きな効果をもたらすこともあるでしょうが、必ずしも期待通りの効果が得られるとは限りません。
失敗した時のダメージを考えると、この場合は「戦略的楽観主義」よりも「防衛的悲観主義」の方が確実性や安全性が高いと言えるでしょう。
大きな経営判断を行うときも同様に、
いざ決断を下すときは、悲観的に考えすぎると思い切った決断ができませんし、不確実なことであればあるほど恐怖を感じるため、収集したデータや自身の直感を頼りにして、楽観的に決める方が早く判断ができます。
そして、決断を下した後はやや悲観的に考えて、慎重にものごとを進める方がいいでしょう。
楽観的に考えていると、日々の細やかな変化を感じ取ることができませんし、気がつけば取り返しのつかない事態を招く可能性があります。
しかし、悲観的な姿勢で対応すると、不安や恐れと真正面から向き合いながら、ものごとを慎重に進めることができるため、結果として最悪の事態に備えることができます。
上記のことから、
決断できない経営者は、決断を下す前と後とで、「戦略的楽観主義」と「防衛的悲観主義」を使い分けることによって、速やかな決断と、確実性や安定性を担保できるというわけです。
経営者が正しい判断を下すために必要なこと
決断できない経営者が、正しい判断を下すために必要なこと、それは、
自分の考えや行動を支持してくれる人間が一人でもいること
です。
正しい判断を迫られた時、自分と同じような思想や考え方や持っている人物がいると、たとえ大勢の人間に反対されたとしても、自分の信念を曲げることなく、落ち着いて冷静に判断することができます。
正しい判断を下すには「心の安定」が必要であり、それを補ってくれる人物や環境などが必要不可欠です。
経営者というポジションは、基本的に孤独で、従業員には決してわからない、経営者だけが抱えている不安や悩み、経営者だからこそ見える景色があります。
そんな時に、たった一人でも心から自分の立場を理解してくれる人がいるという安心感は、心のざわつきを抑え、多数派の意見に惑わされることのない勇気を与えてくれます。
幹部社員の中にそのような人物が一人でもいれば良いのですが、意見や考えを心から支持してくれる人間と、何でもかんでも同調する「イエスマン」とは紙一重ですから、社内でそのような人物を見つけることは簡単ではありません。
この記事をお読みいただいている方の中にも、
「会社の人間には話せないような不安や悩みを、素直に相談できる人物を探している」
「会話の内容が社内に漏れることもなく、客観的な意見や考えを聞ける人はいないものか」
とお考えの経営者もいらっしゃることでしょう。
そのような方は、たった一人でかまいません。
社内外問わず、信頼できる相談相手を、本気で意見交換できるパートナーを見つけてください。
まとめ
今回は
- 決断できない経営者が身につけるべき2つの考え方
- 経営者が正しい判断を下すために必要なこと
についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか?
会社の将来を左右する経営判断は、判断するタイミングが早いか?遅いか?によってその後の展開も変わってくるため、社長の決断力が問われます。
「あの時の決断はやはり正しかった」
「あの時にもし別の選択をしていたら」
当時の決断を振り返ることで、あらためて「会社経営にとって何が大切か」を再認識することもあれば、「社長として何が足りなかったか」と深く反省することもあるでしょう。
大抵の経営判断は、会社が思い描いている未来の姿である「ビジョン」をもとに判断すれば大きく誤ることはないと思いますが、それでも「ほんとうにこの決断は正しいのか?」と常に不安はつきまとうものです。
経営判断は学校で行う試験のように答え合わせができませんから、
「どうすれば正しい決断を下すことができるのか?」
は正直なところ誰にもわかりません。
決断して数ヶ月は正しいと思っていても、1年、3年、5年と時が経つに連れて、それが間違っていたことに気づくこともあるでしょうし、その逆もあるでしょう。
万が一歓迎しない結果が訪れたとしても、それが次につながるものであったり、大切なことに気づかせてくれる出来事であれば、決して判断が間違っていたとは言えない、むしろその判断で良かったと言えるのかもしれません。
いちばん良くないのは
「ああすればよかった」
「こうすればよかった」
と、自ら下した決断についていつまでも後悔することではないでしょうか。
後悔しない選択をすることができれば、その判断は正しかった、その決断は致し方なかったと思えますし、仮に別の判断を下していたとしても、今回とは違った問題が起こっていた可能性もあるわけですから…。
最後にもうひとつ。
「日々の業務に追われて、重要な仕事に費やす時間が足りない…」
「経営戦略や人事、新事業について専門分野の人に相談したい…」
という経営者・役員・マネージャーの皆様に画期的なサービスを2つご紹介いたします。
そのサービスとは、
- オンラインアシスタント
- スポットコンサルティング
です。
オンラインアシスタントとは、経理や総務、人事や労務、財務や法務、営業やマーケティングといった様々な分野の専門的な知識やスキル、実務経験を持った外部(社外)の人材が、オンライン上で自社の業務をサポートしてくれる便利なサービスです。
慢性的な人材不足が続き、リモートワークが珍しいものではなくなった今日、月額数万円から依頼できるオンラインアシスタントが、契約社員やパート社員に取って代わる選択肢のひとつとして、あるいは、多忙な経営者やマネージャーの秘書として活躍してくれます。
スポットコンサルティングとは、ピンポイントで知りたい情報やアドバイスしてほしいことを、特定の業界や業務において豊富な経験を持った「その道のプロ」やコンサルタントに、1時間単位で気軽に相談できる便利なサービスです。
こちらのサービスも、意思決定に欠かせない貴重な判断材料(情報)が安価で手に入ることから、経営者のみならず、管理職や事業責任者、商品の開発責任者など、様々なポジションの方に利用されています。
いずれのサービスも、スピード感を持って会社経営を行う上では利用価値が高いサービスなので、少しでも気になる方は是非チェックしてみてくださいね。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)