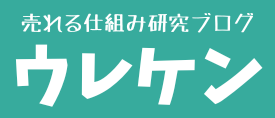「プライシングの具体的な方法が知りたい」
「プライシングを行う際の考え方とは?」
というあなたに、今回は、
- プライシングの方法
- プライシングの考え方
をわかりやすく解説いたします。
プライシングとは、商品(製品)やサービスの価格を設定することを言います。
いわゆる「値付け」ですね。
元アップルコンピュータ日本法人社長で、元日本マクドナルドの代表取締役副会長兼CEOを務めた原田泳幸(はらだえいこう)氏は、プライシングについて…
自社の都合だけで価格を決めたら失敗する。
顧客感情と、利益のバランスをよく見極めて判断しなければ上手くいかない。
とおっしゃっています。
ちなみに原田氏は日本でiMacを大ヒットさせた後、マクドナルドに移ったことから、「マックからマックへ転身」と報道されたそうです。(洒落の内容がスゴすぎて笑えません…)
それともう一人、京セラ創業者である稲盛和夫氏の名言
値決めは経営
は、みなさんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「経営」という一言で表すところが、プライシングの重要性を物語っていますね。
それでは早速みていきましょう。
プライシングの方法
プライシングの方法をご紹介します。
プライシングの方法は全部で5種類。
一般的なプライシングの方法が3種類、新商品のプライシングの方法が2種類あります。
一般的なプライシング
プライシングの一般的な方法は「コスト志向型」「価値志向型」「競争志向型」の3種類。
コスト志向型価格設定
製造や仕入れ(流通)にかかったコストを計算して、一定の利益または利益率を加える設定方法。
価値志向型価格設定
売り手のコストではなく、買い手の価値となるカスタマーバリュー(顧客価値)に基づく設定方法。
競争志向型価格設定
複数の競合他社が販売している類似商品の価格を参考にして、競争力がある価格に設定する方法。
要は製造(仕入れ)コストを基準にするか、顧客に与える価値を基準にするか、競合他社の価格に寄せていくか、ということですね。
新商品のプライシング
新製品を発売する際は、先にご紹介した方法とは異なる2種類のプライシング方法、
- スキミングプライシング
- ペネトレーションプライシング
を用いる場合があります。
スキミングプライシング
スキミングプライシングとは、新商品を市場に投入する際、あえて高価格に設定することで、商品の導入機から高収益を狙う方法です。
画期的な製品や富裕層向けのサービスなど、「高価格を気にしない」ターゲットに有効とされ、市場が成熟するにつれて価格を下げる傾向があります。
スキミングプライシングの事例:携帯電話/パソコン/ゴルフのプレー費/iPhoneやiPad など
ペネトレーションプライシング
ペネトレーションプライシングとは、新商品を発売すると同時に、市場のシェアを一気に拡大することを目的として、顧客ターゲットの予想をはるかに下回る価格に設定する方法で、ペネトレーション価格戦略とも呼ばれます。
ペネトレーション(penetration)は「浸透」という意味。
ペネトレーションプライシングの事例:ヒートテックやエアリズム(ユニクロの下着)など
プライシングの考え方
プライシングする際の「基本的な考え方」について解説いたします。
消費者の立場からすると、価格は安ければ安いほどいいですが、販売する立場からすると、できるだけ高く売りたい。
プライシングとは、消費者と販売者の立場からみた「価格」というものに対して、その落とし所を決める作業と言っても過言ではありません。
「プライシングの基本的な考え方」をお伝えするために、ひとつのエピソードをご紹介しましょう。
ブログ記事の冒頭(アイキャッチ)に使用している写真からもお分かりいただけると思いますが、私は山登りを趣味にしています。
山登りを本格的に始める前、初めて富士山に登った時のことでした。
山頂に立った時の「日本の国土が今この足元にある」という感覚が、今でも忘れられません。
同時に、登山口から山頂に近づくに連れて、山小屋で売られている食べ物や飲み物の値段が少しずつ上がることに驚きつつも、納得させられた記憶があります。
コンビニで売られている120円のジュースが、山頂では500円ほど。
正確な値段は覚えていませんが、何倍もの値段で売られていて、その価格に圧倒されたのを、今でも鮮明に覚えています。
ところが、登山が趣味となり、毎月のように山を訪れるようになると、北アルプスや南アルプスなど、3000m級の高山をいくつも踏破する中で、いつしかドリンクの値段が高いと思うことはなくなり、むしろ、販売してくれている山小屋のみなさんに感謝するようになっていました。
こんなに高い山の上まで、登山者のために重たいドリンクを運んでくださっていることを思うと、価格以上の価値を感じるようになり、次第にその価値を提供してくださっている山小屋の方々に、心から「ありがとうございます!」と思うようになったのです。
山小屋を運営されているみなさまの中に、「ドリンクを高値で販売して一儲けしてやろう!」という方はおそらく誰一人いないでしょう。
プライシングでいちばん大切なことは?
と聞かれたら、私は迷わず「値ごろ感」と答えます。
多くのお客様が「これくらいだったら買う」という価格、とでも言いましょうか。
あるいは「高すぎず安すぎない価格」という表現が正しいのかもしれませんね。
いずれにしても、「値ごろ感」に沿ったプライシングは、やや感覚的なものになると思います。
山小屋で売られているドリンクの価格は、まさに「値ごろ感」をわきまえていて、絶対にそこでしか買えない状況であったとしても、「その値段、ちょっと高すぎるでしょ!」という価格で売られている事はありません。
「まあ、これくらいは当然かな」という価格をほぼ外さない。
だから、登山者は普通にドリンクを買うのです。
中小企業も然り。
プライシングを行う際に競合他社の価格をリサーチして、市場における適正価格から導き出すことも大切ですが、もうひとつ大切な要素として、自社の商品に対する「値ごろ感」を考慮した上で、「この価格なら高くもなく安くもない」という価格に設定することをオススメします。
まとめ
今回は、プライシングの方法や考え方について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
もうひとつ、プライシングを行うときに陥りがちな注意点をお伝えしておきます。
それは、
「ものの値段は、商品やサービスを開発するために費やしたコストとは比例しない」
ということです。
巨額の予算を費やして、長期間にわたって、大勢の人たちの協力によって作られた商品が、必ずしも高額で売れるわけではありません。
反対に、コストをかけずに短期間で作った商品だからといって、値段を安くしなければ売れないというわけでもありません。
映画を例にとってみても、何億円もかけて制作した作品がまったくヒットしないこともあれば、低予算で制作した作品が大ヒットすることもあります。
上記のことから、中小企業や小さい会社が行うべき価格戦略が見えてきます。
つまり、
投資額を増やして良い商品を作ろうとするのではなく、少ない投資で知恵を絞りながら、より多くの商品を生み出すことに重点を置くのです。
開発コストを抑え、競合他社よりも少しだけ価格を安く設定し、利益率もそこそこある
簡単ではありませんが、中小企業や小さい会社は、上記のような商品をひとつでも多く開発することをゴールとすべきでしょう。
そのためには、コストをかけずに、たくさん試して、ダメなら止める。
最後にもうひとつ。
- 少人数かつ低予算で「売れる仕組み」を作りたい
- Web媒体を活用した集客や販売を強化したい
- Webマーケティングの知識やスキルを身につけたい
という方に、おすすめの「Webマーケティングスクール・講座」をご紹介いたします。
ビジネスの現場で通用する「実務レベルのWebマーケティング力」を独学で身につけるには、多くの関連書籍を読んで、実際に手を動かしながら、トライアンドエラーを何度となく繰り返すことになります。(私自身がそうであったように…)
その点、Webマーケティングスクールでは座学と実務をバランスよく取り入れた実践的なカリキュラムをこなすことによって、効率良くWebマーケティング学べるだけでなく、わからないことがあっても現役Webマーケターが疑問や質問に答えてくれるので安心です。
以下の記事では、
- Webマーケター志望の大学生や、キャリアアップを目指す社会人を対象としたスクールを9つ
- 社内Webマーケターを目指す方や、販売責任者・Web担当者を対象としたスクールを7つ
計16個のWebマーケティングスクール・講座をご紹介するとともに、各スクール(講座)の特徴や自分に合ったスクール(講座)の選び方をわかりやすく解説しておりますので、少しでもご興味がある方は是非チェックしてみてくださいね。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)