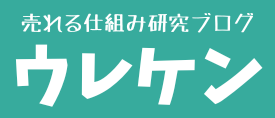「自分の頭で考える力を養うにはどうすればいいか?」
「自発的に考えて行動する部下を育てる方法とは?」
「自立型人材を育てる有効なサービスを探している」
というあなたに、今回は
- 自分の頭で考えて、自発的に行動する部下の育て方
- 自発的に動ける人を育てる際に有効なサービス
をご紹介します。
企業は人の集合体ですから、所属する人の成長無くして、企業が成長することはありません。
では、人が成長するとはどういうことか?
誤解を恐れず言うならば、それは「自分の頭で考えて、自発的に動けるようになること」です。
そして、従業員ひとりひとりが、自分の頭で考えて動く組織、つまり「自走する組織」を作るためには、「自発的に動ける人=自立型人材」を一人でも多く育てる意外に方法はありません。
本記事では、「自分の頭で考えて動ける部下の育て方」について具体例を挙げながら解説するとともに、自発的に動ける人を育てる際に有効とされる画期的なサービスをご紹介いたします。
コーチングやビジネスリーダーに関連する数々の書籍を読みあさり、過去に部署の主任やリーダーを任され、マーケティング部のサブマネージャーや営業部長を務めた経験を持つ筆者が、どこよりもわかりやすく解説・ご紹介いたしますので、
- 「部下が自主的に動けないので困っている…」という上司の方
- 「自立型人材の育成に力を入れたい」という経営者やマネージャーの方
は、ぜひ参考になさってください。
それでは早速みていきましょう。
自分で考える力を養うには?

自分で考える力を養うにはどうすればいいか?
結論から申し上げると、「まずは自分の頭で考えることを日々の習慣にする」ことです。
顧客のニーズに応え続けるためには、顧客の声に真摯に耳を傾けながら、世の中の微細な変化に気づき、それらをもとに
「何をすべきか」
「どうあるべきか」
「どのようにすべきか」
を自分の頭で考え、それを行動に移す以外に方法はありません。
会社に属する全ての従業員が、自分の仕事に対して
「改善できるところはないか?」
「ミスを減らす方法はないか?」
「もっとシンプルにできないか?」
「コストを下げるためにはどうすればいいか?」
など、自分の頭で考えて行動する習慣が身につくと、会社は劇的に変化します。
自分の頭で考えた全ての行動がうまくいくとは限りませんが、
「失敗は成功の元」
と言われるように、失敗した経験も必ず糧となります。
自分の頭で考えて行動したことであれば、尚更その失敗から得られるものは大きいでしょう。
「最初からうまくいくことは稀だ」
と、あらかじめ失敗することを見積もって、多少は間違ってもいいから自分の頭で考えて行動することを会社が推奨し、そのような風土を根付かせることによって、全社員に成長する機会を与える企業こそ、より多くの価値を生み出せる企業に成長します。
業績を上げるためには、会社の成長を促す「売れる仕組み」が必要であり、会社が成長し続けるためには、何よりも個々の社員が成長する環境を整えることが重要です。
とは言うものの、個々の社員が自分の頭で考える習慣を身につけて、自ら率先して行動するようになることは簡単ではありません。
では、「自分で考える力」を養うために、従業員が自分の頭で考える習慣を身につけるためにはどうすればいいのでしょうか?
そして、会社が「自走する組織」に生まれ変わるためにはどうすればいいのか?
自分で考える力の育て方

「自分で考える力」の育て方をご紹介します。
経営者や多くの社員を束ねるマネージャー、部下を持つ上司の方は、常々
「自分の頭で考えて動く部下を育てたい」
と思っているのではないでしょうか。
例に違わず、私も部下ができて間もなく、同じ悩みを抱えていました。
この後ご紹介する方法は、私自身が実際にいろんな方法を試した結果、最も効果を感じることができた方法です。
人によってはうまくいかないこともありますし、少々時間がかかるかもしれませんが、これからご紹介する方法を根気よく実践することで、部下の「自分の頭で考える力」を養い、部下に自分で考える習慣を身につけさせることができます。
その方法とは、結論から申し上げると、
「上司が答えを言わない」こと、これに尽きます。
わかっていても言わない、聞かれても言わない、とにかく答えを部下に考えさせるのです。
例えば上司が部下に指示する時も、具体的な手順や方法を事細かに伝えることなく、
- やりたいこと
- 達成したいこと
- 得たい結果
だけを伝えて、自分の頭で考えて答えを見つけさせるように質問を投げかけるのです。
例えばこんなこんな感じ。

「顧客ターゲットをもう少し明確にしたいんだけど、何かいい方法はないかな?」
「この商品のここを改善すればもっと良くなると思うんだけど、どうすればいいと思う?」
「半年後までにこの数字を達成したいんだけど、まず何から始めたらいいかな?」
質問をするときのポイントは、相談を持ちかけるような感じで話しかけることです。
決して「明日の正午までに3案出してくれ」と言ってはいけません。
逆に部下のプレッシャーを下げるために、以下のような一言を付け加えると良いでしょう。

「どんな考えでもいいから聞かせてくれるかな?そこから別のアイデアが思い浮かぶこともあるから」
「私も考えているんだけど、なかなかいいアイデアが浮かばなくて困っているんだ…力を貸してくれるかな?」
このような形で質問を投げかけられると、質問を受けた社員は
「自分の意見を聞きたがっている」
「自分を頼ってくれている」
と感じますから、俄然真剣に考えます。
人間は期待をかけられると、それに応えようとしますから(ピグマリオン効果と言います)、その効果は絶大です。
なお今まで自分で考える機会がなかった社員は、すぐに答えを見つけることができませんから、質問を投げかける上司もあまり期待してはいけません。
むしろ自分に協力してくれたことを評価して、さらに深く考えさせるような質問を投げかけてみましょう。
具体的には…

「なるほど、確かにそういう方法もあるね。」
「その考えは自分には思いつかないなぁ。貴重な意見をありがとう。」
と、考えてくれたことに対する感謝の言葉をかけた上で、以下のような質問をしてみるのです。

「ただ今回はこっちの方向で進めたいと思っているから、そのあたりを修正して、もう一度意見を聞かせてくれないかな?」
「ただその方法だと今季の予算を超えてしまう恐れがあるから、もう少しコストを抑えるような工夫はできないだろうか?」
上記のように具体的な要望を追加して質問を重ねていくと、それを踏まえた上でさらに考えを深めてくれます。
おそらく次に帰ってくる回答は、最初の回答に比べると格段に的を得たものになっているはず。
このような形で上司と部下が「質問と回答のキャッチボール」を続けると、より良い答えに辿り着ける確率が上がります。
このキャッチボールを習慣化することで、自分の頭で考える力が確実に身につきます。
なお、考える力の育て方を実践するためには、上司の根気や忍耐が必要不可欠となりますから、すぐに結果が出なくても、ぜひ長い目で部下とキャッチボールを続けていただければ幸いです。
自発的に行動させるには?

次に、部下に「自発的に行動させるにはどうすればいいか?」
について解説いたします。
結論から申し上げると、「考える力」が身につけば、部下は自発的に行動するようになります。
「質問と回答のキャッチボール」が習慣になると、上司が質問をせずとも部下が自ら問題を発見し、それに対する回答を自分で考えるようになり、提案という形で上司に伝えるようになります。
では、なぜ部下が自ら提案するような状況が生まれるのか?
2つの理由が考えられます。
まずひとつ目の理由は「主体性が芽生える」から。
「質問と回答のキャッチボール」を続けることで、部下は良くも悪くも
「この人は基本的に私に明確な指示を出してくれない」
ということがわかってくるので、「自分が考えて動かなければ」という意識が芽生えます。
もちろん個人差もあるので、うまくいかない場合は様子を見ながら根気よくキャッチボールを続けるしかありません。
「なぜ細かい指示を出してくれないんですか?」
と尋ねられることもあるでしょう。
その時は正直に「自分で考える力をつけてほしいから」と伝えましょう。
2つ目の理由は「期待に応えようとする」から。
部下は上司からの質問に答え続ける過程で、自分でも回答の質が上がっていることを実感すると同時に、自分の意見に耳を傾けてくれる上司に対して、少なからず信頼を寄せるようになります。
さらには
「上司の期待に応えたい」
「上司に評価されたい」
と思うようになるため、次第に上司から質問されるのをじっと待つことなく、自ら問題点や改善点を見つけ、提案するようになるというわけです。
全ての部下が、自発的に行動を起こすようになるわけではありませんが、ことあるごとに
「日々の仕事で何か気づいたことや改善すべき点があれば教えてくださいね」
と部下に伝えておくと、その確率は高まるでしょう。
部下が自分で考える力を身につけて、自ら率先して行動するようになると、初めのうちは失敗することの方が多いため、それをうまくフォローしてあげることも大切です。
部下の自発的な行動が原因となって発生した失敗やミスを責めると、
部下は「もう2度と自分の判断では動かないようにしよう」
という気になりますから、失敗やミスが起きてもグッと我慢して、部下とともに
「どうすればよかったのか?」
「失敗の原因は何だったのか?」
について一緒に考える時間を作りましょう。
その際も上司は質問をするだけで、失敗の原因を部下に考えさせることが大切です。
「何に気をつけなければならないのか?」
「何が足りなかったのか?」
など、自分の頭で考えることによって、「自分には何が足りなかったのか?」を理解できます。
自分で考えて行動する部下を見守る

自分の頭で考える、そして、自発的に行動する部下を養うためには、上司はできるだけ手を差し伸べることなく、自分で考えて行動する部下を見守る姿勢が必要不可欠です。
会社が「自分で考えて行動する集団」に成長するためには、詰まるところ、
上司が根気よく部下の成長を見守ることができるかどうか?
にかかっているといっても過言ではありません。
一般的には部下よりも経験を積んだ社員が上司になるわけですから、なかなか答えを見つけられない部下を見てヤキモキすることもあるでしょう。
時には、
- 自分でやった方が早いし、間違いが少ない
- こちらから明確な指示を出した方が効率が良い
- 失敗する部下の尻拭いをするのは勘弁してほしい
と思うことも多々あるでしょう。
しかし、常に上司が指示を出していたのでは、いつまで経っても「自分の頭で考える部下」を育てることはできません。
自分の頭で考える部下が育たないということは、「自走する組織」が育たないことを意味します。
ヤキモキしたり、イライラするときはそのことを思い出して、部下に対して穏やかな対応を心がけ、部下が成長するまで温かく見守ってあげてください。
「自分で考える部下が育つまでに、会社の存続が危ぶまれる」
という場合は、全ての社員に自発的な行動を促すのではなく、まずはやる気がある社員やモチベーションが高い社員にだけ「質問と回答のキャッチボール」を試みるのもひとつの方法です。
最後にもうひとつ。
質問と回答のキャッチボールは、部下を信頼することから始まります。
「必ずキャッチして、投げ返してくれる」
と、無条件に上司が部下を信じることが何よりも大切です。
そうやって育った部下がいつしか上司になり、自分の部下を持つようになれば、きっと自分の部下のことを心から信じて、根気よく「質問と回答のキャッチボール」を行ってくれることでしょう。
自発的に動ける人を育てるサービス
自発的に動ける人を育てる画期的なサービスをご紹介いたします。
そのサービスとは、【flier(フライヤー)法人版】です。

【flier(フライヤー)法人版】は累計導入社数700社以上、継続率が99%を誇る、1冊10分で読める「本の要約コンテンツ」を軸にした人材育成サービスで、人事のコミュニティ【日本の人事部】が主催する「HR Award」では、2021年度の人事開発・育成部門において最優秀賞を受賞しています。
では、なぜ本の要約サービスを自社に導入することで自発的に動ける人、つまり、自立型人材を育てることができるのか?
そのヒントは、「社員が自ら学ぶ環境づくり」にあります。
人は誰かに指示されて行った仕事よりも、自発的に行った仕事の方が成果に対する達成感や充実感を得やすく、うまくいったときの喜びや満足感も大きくなります。
しかしながら、「自ら学ぶ習慣」のない人が、いきなり自ら考えて行動することは極めて稀であり、加えて、自発的に考えて行動するメリット(利点)やベネフィット(効果や恩恵)を知らなければ、単純に「うまくいかなかったとき」のことを考えるとデメリットの方が大きいため、誰も自発的に行動しようとは思いません。
自発的に動ける人は日頃から学習する習慣が身についており、自分の頭で考えて行動することによるメリットやベネフィットも理解しています。
そして、自発的に動ける社員を育てるには、回りくどいと思われるかもしれませんが、まずは社員に自ら学ぶ習慣を身につけさせることが必要不可欠であり、自ら学ぶ習慣が身につけば、ビジネスに有効な知識や考え方を知ることができますから、それらを「試す機会」を求めるようになるというわけです。
つまり、社員が自ら学ぶ環境を整えてあげることで、自立型人材が育つというわけです。
1冊10分で読める要約コンテンツ【flier(フライヤー)法人版】は、以下の通り、充実の内容&多彩な機能を備えているので、本を読む習慣がない社員も学び続けることができます。
【flier(フライヤー)法人版】の主な特徴
- 全17カテゴリ3,100冊超の要約を、1冊10分でインプットできる
- 経営者や大学教授が「ビジネスパーソンが今読むべき本」を選書
- 著者や出版社お墨つきの高品質な要約が、毎日1冊ずつ追加される
- 要約を読んだ際の学びや気づきを社員同士でシェアできる機能も
- 「ながら読書」できる音声機能付き。1.5倍、2.0倍の倍速対応可
- 社員の利用状況が一覧できる管理画面。オススメ通知で利用促進
加えて、ビジネスに関連する様々なカテゴリの要約を読むことで、アイデア出しや商品企画に活かしたり、営業パーソンの話のネタにも使える他、社員間のコミュニケーション活性化や会社の福利厚生としても有効です。
【flier(フライヤー)法人版】のビジネス関連カテゴリ
- スキルアップ・生産性・時間管理・リーダーシップ・マネジメント
- 企業・イノベーション・人事・経営戦略・マーケティング・トレンド
- 政治・経済・テクノロジー・IT・産業・業界・グローバル
- 健康・フィットネス・自己啓発・サイエンス・リベラルアーツ
利用料金
- 20名から導入可能で、アカウント数に応じて料金は異なる。
- アカウント数が多ければ一人あたり月々数百円で利用できる。
導入までの流れ
- 公式サイトの「資料ダウンロード・無料トライアル」を申し込む(3営業日以内に連絡有)
- サービスの説明やヒアリングを行った後、お見積りや最適な活用方法を提案してくれる
- 正式に利用を申し込むと、申込書に記載された「利用開始日」に管理画面が渡される
- 「社員が自ら学ぶ環境」を整えることによって「自立型人材」を育てたい企業様
- 社員の自己啓発を促したい、ビジネス関連の読書を推奨したいとお考えの企業様
- 社員間のコミュニケーション活性化や、会社の福利厚生として活用したい企業様
【flier(フライヤー)法人版】が少しでも気になる方をはじめ、
- まずは【flier(フライヤー)法人版】がどんなサービスか詳しく知りたい
- 導入している企業の事例や、具体的にどんな効果が期待できるのか知りたい
- 詳しい資料や利用料金(見積もり)を確かめてから、社内で検討したい
という方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
まとめ
今回は、
- 自分の頭で考えて、自発的に行動する部下の育て方
- 自発的に動ける人を育てる際に有効なサービス
ついて解説、ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、もう一度おさらいしておきましょう。
自分の頭で考えて、自発的に行動する部下の育て方
- 部下が自分の頭で考えることを日々の習慣にするために、上司が答えを言うことなく、部下と「「質問と回答のキャッチボール」を根気よく続ける。
- 部下が自発的に行動したことによる失敗の原因を一緒に考え、日頃から部下に対して穏やかな対応を心がけ、部下が成長するまで温かく見守る。
自発的に動ける人を育てるサービス【flier(フライヤー)法人版】

累計導入社数700社以上、継続率が99%を誇る、1冊10分で読める「本の要約コンテンツ」を軸にした人材育成サービス。「社員が自ら学ぶ環境」を整えることによって「自立型人材」を育てたい企業様におすすめです。
山本五十六氏の有名な言葉
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」
をご存知でしょうか。
この文章だけを読むと、「率先垂範(先に立って模範を示すこと)が良い」と解釈できます。
しかし、実はこの文章には続きがあります。
実際は、
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
と、続くそうです。
これを上司と部下の関係に当てはめると、
部下と会話のキャッチボールを行い、部下の意見や考えをいったん受け止めて、自ら考えさせて、行動させなければ、部下は育たない。
そして、部下が自らの意思で行動する際は、部下を信頼して、感謝しながら見守ることが大切である。
そんな風にも解釈できます。
みなさんはどのように解釈しますか?
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました (^.^)
以下、この記事を読んでくださった方へ「オススメの記事」をピックアップしましたので、お時間がございましたらぜひご一読くださいませ。