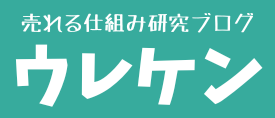「中小企業や小さな会社にマーケティングを根付かせる方法は?」
「中小企業の課題とされるマーケティングが社内に浸透しない原因は?」
「マーケティングを定着させるにあたって、最初にすべきことは何?」
というあなたに、今回は、
- 中小企業の課題とされる「マーケティング」が社内に浸透しない原因
- マーケティングを定着させるために、まず初めにすべきこと
について解説いたします。
マーケティングとは、一言で言うと「売れる仕組みづくり」です。
マーケティングが社内に浸透すると、具体的にどのような変化が起こるのか?
わかりやすく言うと、人に依存する営業活動をストップすると売上がガクンと下がる…そんな状態から、人が営業活動を行わずとも、「ぜひ御社の商品を売ってください」と、お客様の方から声をかけていただけるようになります。
マーケティングが加速すると商品のファンが増え、それに伴って会社のファンも増えます。
人に依存する営業活動がなくなることで時間的な余裕も生まれますから、既存商品の改善や新たな事業への投資、人材育成に力を入れることもできるでしょう。
社内にマーケティングを定着させることなく、上記の好循環を生み出すことはできません。
ではマーケティングを社内に定着させるためには、まず初めに何をすべきか?
まずは「中小企業にマーケティングが浸透しない原因」から見ていきましょう。
中小企業は「マーケティングの浸透」が課題
中小企業が抱える大きな課題のひとつに「マーケティングが浸透しない」というものがあります。
中小企業にマーケティングが浸透しない主な原因は、
- マーケティングについての理解が乏しい
- マーケティングができる人材がいない
- マーケティングに費やせる予算が少ない
と考えられます。
社内に「マーケティング部」を設けている会社も多くはないでしょう。
個人的な所感となりますが、中小企業の多くは、良くも悪くも「商品やサービスありき」です。
「いい商品を作ること」
「いいサービスを提供すること」
を最優先事項として、日々、一生懸命に取り組んでいらっしゃる企業様が多く見られます。
しかしながら「いい商品を作る」ことと、「売れる商品を企画する」ことや「商品の魅力をPRする」ことは別物です。
全ての中小企業に当てはまるわけではりませんが、多くの中小企業は「商品を作る」ことは得意であっても、「どんな商品を、どこで、どのように売るか?」を考えることに関しては、あまり得意ではないように感じます。
そして、ここに中小企業が取り組むべきマーケティング課題があります。
限られた人数で日々の業務と格闘し、一人でいくつもの担当を掛け持ちしながら、目の前のお客様に真摯に対応する毎日…。
そんな状況で各部署の責任者が集い、頭を切り替えて
「どんな商品を、どこで、どのように売るか?」
といったマーケティング戦略を立案することは、現実的に難しいのかもしれません。
よくある話ですが、とりあえず現状分析を行ってはみたものの、市場に出回っている売れ筋商品をリサーチして、それに対抗するかのように
「他社よりも価格を下げる」
「他社よりも機能を増やす」
「他社よりもラインナップをそろえる」
など、商品開発のスタートラインが「他社製品」に依存している中小企業も多々見受けられます。
プライシング(価格設定)をするときも他社の価格を基準にして、できるだけ他社よりも安く売る。
どこで売るか?
どのような広告宣伝を行うか?
を決める際も、他社の広告や販売ルートを参考にして、他社と似たような場所や、似たような広告を出す…。
他社を基準にしたり、他社を参考にすることは決して悪いことではありません。
むしろ他社の動向をチェックすることは必須です。
しかし、他社を気にしすぎるあまり、自社独自の魅力や顧客のニーズを追求しないまま、表面的なマーケティング活動を行ったとしても、残念ながら大きな効果は期待できません。
では、
マーケティングについての理解が乏しく
マーケティングができる人材もいない、
マーケティングに費やせる予算も少ない…
そのような課題を抱えた状態で、どうすればマーケティングを自社に根付かせることができるのか?
中小企業にマーケティングを定着させるには?
中小企業や小さな会社に、マーケティングを定着させるにはどうすればいいか?
単純に、まずは経営者自らが「マーケティングへの理解を深める」ことが第一。
とはいうものの、人は自分がうまくいった過去のやり方や成功体験に執着する生き物ですから、今まで聞いたこともない「マーケティング」という言葉を聞いて、理由もなく拒絶反応を示す経営者もいらっしゃることでしょう。
そこで、いったん「マーケティング」という言葉から離れ、最終的にマーケティング活動につながる考え方や行動を取り入れてみるのです。
具体的には、以下の3つの方法をオススメします。
中小企業にマーケティングを定着させるために
- ビジネスの常識を疑い、視点を変えてみる
- 未来から逆算して考える習慣を身につける
- 優先度が低い仕事を手放して、時間を作る
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
ビジネスの常識を疑う
中小企業にマーケティングを定着させるために、ビジネスの常識を疑って、視点を変えてみましょう。
正確には、ビジネスの真理(変わらないものや考え方)と、疑うべき常識を見極めて、後者を違った角度から眺めてみる。
新しい考え方を素直に吸収するのは、とても難しいことだと思います。
ましてやビジネスを行う上で常識とされていることに反して、まったく異なる行動をとることは、さぞかし抵抗があることでしょう。
しかし、身の回りの生活に置き換えてみるとお分かりいただけると思いますが、今常識と思っていることは、数年前まで非常識と言われていたことが多々ありますし、逆に今常識と思っていることが、数年後には世間から非常識だと思われることもあります。
常識とは現時点においての正しいとされる価値観や知識、判断力のことを指しているだけで、それらの考えが未来においても通用するとは限りません。
マーケティングとは「売れる仕組み」を作ることと同義ですから、新たな売れる仕組みを作るためには、常識を疑う視点が求められます。
未来から逆算して考える
中小企業にマーケティングを定着させるために、未来から逆算して考える習慣を身につけましょう。
「過去」の延長線上に「今」があることは事実ですが、「今」の延長線上に「未来」があるのかと言われると、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
なぜなら、「今どのような選択をするのか?」「今どのような行動をとるのか?」によって未来が大きく変わるから。
であるならば、まずは
「こうありたい」
「こうあるべきだ」
「こんな未来を創りたい」
という、未来のゴールを先に設定して、そのゴールに向けて今の考えや行動を決めることができれば、きっと心に思い描く未来に近づけるのではないでしょうか。
マーケティングとは「売る」のではなく、「売れる」状態を作り出すことです。
つまり、「売れている」未来の状態をイメージすることから始め、どうすれば「売れている」未来に近づけるか?と考えてみる。
そのロードマップを描くことが、まさにマーケティングなのです。
時間をつくる努力をする
中小企業にマーケティングを定着させるために、今行っているお仕事をあらためてリストアップして、優先度が低い仕事を手放し、時間を作りましょう。
「忙しすぎて昼食をとる時間もない」
「時間がいくらあっても足りない」
「ここ数ヶ月ほど残業が続いている」
そんな方は、あらためて仕事の棚卸しを行うことをオススメします。
- これはほんとうに自分がやらなければならない仕事か?
- 別の人に任せることはできないか?
- この仕事をお断りするという選択肢はなかったか?
- もっと合理的な方法はないか?
など、あらゆる側面から自分の仕事を見直してみましょう。
「こうあるべき」という考え方が根付いた原因は何か?
を辿っていくと、実は単に自分が執着していただけ…ということも多々あります。
くどいようですが、何か新しいことを始めるためには、これまで行っていた仕事を手放さなければなりません。
これは必然です。
今の仕事を手放すことができなければ、新たな試みをスタートすることは難しいでしょう。
もちろん、マーケティングも例外ではありません。
まとめ
今回は、中小企業の課題とされる「マーケティングが浸透しない」原因と対策について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
もう一度、中小企業にマーケティングを定着させるための3つの取り組みについて、おさらいしておきましょう。
中小企業にマーケティングを定着させるために
- ビジネスの常識を疑い、視点を変えてみる
- 未来から逆算して考える習慣を身につける
- 優先度が低い仕事を手放して、時間を作る
自分たちのお給料は、自分たちで稼がなければなりません。
とりわけ中小企業に勤める従業員は、日々そのような姿勢で仕事と向き合うことが大切です。
私は大企業で働いたことがないので、大企業で働くことがどういうものなのかわかりませんが、中小企業はお客様からの注文が少なくなると、社内の雰囲気が明らかに変わります。
売上が芳しくない状態が数ヶ月ほど続くと、口には出しませんが、従業員の間で妙な危機感が漂うようになり、社内の空気はピリピリ、社長のご機嫌は最悪、そんな会社も多いのではないでしょうか。
私もそのような場に何度も居合わせたことがありますから、あの何とも言えない嫌な雰囲気は2度と経験したくありません…。
業績を安定させるには、マーケティングを社内に根付かせる必要があります。
そのためには、経営者の行動力が必要不可欠です。
経営者は「行動のリーダー」でなければならない。
現実に商売を創り、戦略ストーリーを構想し、ストーリーを動かし、稼ぐ。
こうした本来の経営という仕事は、いずれも「何をするのか」「何をしたいのか」という経営者の行動を問うものであり、運動エネルギーにかかっている。
出典:楠木 健(2014)『「好き嫌い」と経営』東洋経済新報社 .
まずは、社内で最も影響力が高い社長が、率先して行動する。
それが、マーケティングを社内に定着させる「最短ルート」と言えそうですね。
最後にもうひとつ。
「日々の業務に追われて、重要な仕事に費やす時間が足りない…」
「経営戦略や人事、新事業について専門分野の人に相談したい…」
という経営者・役員・マネージャーの皆様に画期的なサービスを2つご紹介いたします。
そのサービスとは、
- オンラインアシスタント
- スポットコンサルティング
です。
オンラインアシスタントとは、経理や総務、人事や労務、財務や法務、営業やマーケティングといった様々な分野の専門的な知識やスキル、実務経験を持った外部(社外)の人材が、オンライン上で自社の業務をサポートしてくれる便利なサービスです。
慢性的な人材不足が続き、リモートワークが珍しいものではなくなった今日、月額数万円から依頼できるオンラインアシスタントが、契約社員やパート社員に取って代わる選択肢のひとつとして、あるいは、多忙な経営者やマネージャーの秘書として活躍してくれます。
スポットコンサルティングとは、ピンポイントで知りたい情報やアドバイスしてほしいことを、特定の業界や業務において豊富な経験を持った「その道のプロ」やコンサルタントに、1時間単位で気軽に相談できる便利なサービスです。
こちらのサービスも、意思決定に欠かせない貴重な判断材料(情報)が安価で手に入ることから、経営者のみならず、管理職や事業責任者、商品の開発責任者など、様々なポジションの方に利用されています。
いずれのサービスも、スピード感を持って会社経営を行う上では利用価値が高いサービスなので、少しでも気になる方は是非チェックしてみてくださいね。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)