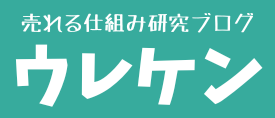「配置転換を行う目的とは?」
「配置転換にはどんなメリットがある?」
「配置転換の考え方がわからない」
というあなたに、今回は
- 配置転換の本来の目的
- 配置転換の主なメリット
- 配置転換の成功事例
について解説します。
配置転換は、ただ単に
- 仕事ができない人や、能力不足と判断された社員を別の部署に異動させる
- 病気やストレス、人間関係が原因で、仕事に支障をきたしている人を異動させる
- モチベーションが下がっている社員を異動させることで、やる気を起こさせる
ことではありません。
結果として上記のような社員に異動していただくこともありますが、配置転換は社内に良い風を吹かせるためのきっかけ作りであり、前向きでポジティブな施策です。
そして、配置転換が前向きでポジティブな施策であることを、従業員に浸透させるためには、明確な目的を持って配置転換を行う必要があります。
では、配置転換を行うとき、どのような目的を持って、どのように取り組むべきか?
早速見ていきましょう。
配置転換の目的
配置転換の目的をお話しする前に、配置転換の意味を簡単に確認しておきましょう。
配置転換とは人事異動のひとつで、従業員の配置を変更することです。
同じ会社の中で職務内容や就業場所、勤務地などを変更するもので、配転(はいてん)やローテーションと呼ばれることもあります。
なお別の事業所(勤務地)に配転される場合は「転勤」、関連会社や子会社への配置転換は「出向」と言います。
それでは、あらためて配置転換の目的について解説します。
配置転換の目的はただひとつ、
「人的資源を再配分することによって費用対効果を高めること」
に他なりません。
配置転換は、この目的を果たすために行われます。
具体的には、
- 従業員を適材適所に配置することで、パフォーマンスの向上を図る
- 職場環境を変えて初心を思い出させることで、組織の活性化を図る
- 社内のトップパフォーマーを集めることで、新規事業を成功させる
- 様々な部署を経験させることで、リーダーや幹部候補生を育成する
- 希望の部署に配属することで、モチベーションの維持・向上を図る
といった取り組みが、本来の目的を意識した配置転換と言えるでしょう。
「仕事ができない社員」「能力が不足している社員」を配置転換する場合もあるでしょうが、その場合も、配置転換の本来の目的を忘れることなく、上記の取り組みを行うことで会社全体の費用対効果を高めるように務めることが重要です。


配置転換のメリット
配置転換を行う主なメリットをご紹介します。
配置転換のメリット
- 部署の雰囲気を変えて、良い流れを呼び込むことができる
- 過去の自分をリセットして、新たなスタートが切れる
- 社員の能力を開花させ、活躍の場を提供することができる
最も大きなメリットは、これまで目立った成果を上げることができなかった社員が、仕事の内容や働く場所を変えることで、あるいは上司や一緒に働く仲間を変えることによって、これまでの自分をいったんリセットできることでしょう。
新しい環境は仕事への意欲を高め、自身のモチベーションを上げる大きな要因となります。
そして、過去の環境をリセットできる「配置転換」は、社員の能力を開花させるだけでなく、上司との絆を深め、信頼関係を築く良いきっかけになるのではないでしょうか。
人には得手不得手や向き不向きがあり、能力を活かせる場所もあれば、そうでない場所もあります。
小学生の頃を思い出してください。
国語、算数、理科、社会など、いろんな教科があったかと思いますが、
「全ての教科が苦手…」
という子供はあまりいません。
飛び抜けて優秀な成績を修めることができなくても、自分の中で
「この教科好きだな〜」
「この教科は不思議と苦にならない」
というものが一つや二つはあったはずです。
仮に全ての教科が苦手だったとしても、
「面白いことをして友達を笑わせるのが得意」
「好き嫌いなく給食を残さず食べる」
「図書館でいちばんたくさん本を借りて読んだ」
など、何かしら人に自慢できることや、人よりも優れたものがあったのではないでしょうか。
(よく思い出してください!きっとあるはずです)
ちなみに私が得意としていた科目は先に挙げた主要な4教科ではなく、体育と図工と音楽でした…。
上記のように小学生の頃はいろんな教科があったけど、社会人になって企業に勤めると、好き嫌いに関係なく与えられた仕事をこなさなければならず、いろんな仕事を一通り試すことは叶いません。
自分が苦手とする仕事が与えられた時、当然ながら結果を出すことは難しく、長期間にわたって結果が出なければ、「仕事ができない」というレッテルを貼らてしまいます。
そうなると、なんとか結果を出そうと頑張りますが、なかなかうまくいかないのが現実です…。
もしそのような社員が社内にいるのであれば、彼や彼女らが仕事に対する自信を失ってしまう前に、できるだけ早く配置転換を行うことをオススメします。
配置転換の成功例
ここで配置転換によって輝きを取り戻した成功例をご紹介したいと思います。
「野村再生工場」という言葉をご存知でしょうか。
プロ野球ファンであれば説明は不要ですが、そうでない方もいらっしゃるかと思いますので、あらためてご説明いたします。
野村再生工場とは「ID野球」で知られる野村克也氏がプロ野球の監督時代に、戦力外を通告された他球団の選手の中から、「まだ活躍できる」と(野村監督が)判断した選手を獲得し、自身の助言や指導によって再び活躍できる機会を与えることに対して名付けられた愛称です。
会社に例えると、プロ野球という大きな会社の中で部署が変わり、新しい上司のもとで仕事をするといったところでしょうか。
では所属する球団や監督が変わったことによって、具体的に何が起きたか?
驚くべきことに、移籍するまで1勝も上げられなかったピッチャーが、移籍後の4年間で50勝を超える勝ち星をあげたり、自由契約となった(戦力外を言い渡された)選手が新天地で開幕戦のクリーンナップを任され、3打席連続ホームランを放つなど、これまで「結果が出なかった」選手が、新しい環境と新しい上司のもとで、誰もが認める輝かしい結果を残したのです。
もし別のチームに移ることなく、同じチーム内で選手生活を送っていたら、上記のような結果を残せたか?と言われると、それは誰にもわかりませんが、「配置転換」が大きなきっかけとなり、転機となったことは誰もが認めるところでしょう。
もちろん環境の変化だけが結果につながったわけではありません。
新たな環境で心機一転し、選手自ら今まで以上に努力もしたでしょうし、今まで以上に監督のアドバイスを素直に聞き入れるようになったことも、結果を残すことができた大きな要因だと思います。
それらも含め、最も大きなきっかけとなったのが「配置転換」なのです。
まとめ
今回は、
- 配置転換の本来の目的
- 配置転換の主なメリット
- 配置転換の成功事例
についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、最後にもう一度、
「配置転換の目的と取り組み方」について確認しておきましょう。
配置転換の目的
人的資源を再配分することによって費用対効果を高めること
配置転換の取り組み方
- 従業員を適材適所に配置することで、パフォーマンスの向上を図る
- 職場環境を変えて初心を思い出させることで、組織の活性化を図る
- 社内のトップパフォーマーを集めることで、新規事業を成功させる
- 様々な部署を経験させることで、リーダーや幹部候補生を育成する
- 希望の部署に配属することで、モチベーションの維持・向上を図る
売上が低迷している状況では、できるだけコストをかけずに業績をV字回復させる必要がありますから、今ある資源を有効に活用することが求められます。
資源というと、使える予算や会社が保有している設備だけをイメージする方もいらっしゃいますが、人も会社の貴重な資源ですから、活用しない手はありません。
パソコンやその他の機材はスペックが決まっていて、OSをアップデートしたり、部品を交換しない限りパフォーマンスを挙げることはできませんが、面白いことに、人は仕事の内容や働く環境、上司や周りのメンバーが変わると隠れた能力を発揮することがあります。
上記のことから、売上が低迷している時や、経営資源が限られている時ほど、本来の力を発揮できていない社員のパフォーマンスを上げることが重要です。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました (^.^)
以下、この記事を読んでくださった方へ「オススメの記事」をピックアップしましたので、お時間がございましたらぜひご一読くださいませ。