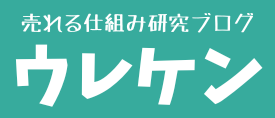「従業員に配置転換の理由をどのように伝えるべきか…」
「配置転換の伝え方のコツが知りたい」
「不当な配置転換と思われないためのポイントは?」
というあなたに、今回は
- 配置転換の理由を当事者に伝える時の3つのコツ
- 不当な配置転換を見分けるためのチェックリスト
を解説します。
従業員にとって、突然の配置転換はまさに「青天の霹靂(へきれき)」です。
気持ちを切り替えて、前向きに捉えてくれる人もいれば、当然ながら変化を嫌う人もいます。
と同時に、
配置転換の理由をどのように伝えるか?
によって、配置転換を告げられる当事者の受け止め方も大きく変わります。
配置転換をチャンスと捉え、自身の成長のきっかけやキャリアアップの足がかりと受け止めてもらうことができれば、従業員にとっても、会社にとっても大きなプラスです。
対照的に、万が一「不当な配置転換」と判断されるようなことがあれば、従業員の仕事に対するモチベーションは下がり、会社に対する不信感が増して、最悪の場合は退職する可能性もゼロではありません。
そんなことにならないように、配置転換の理由を伝えるときは、心から納得してもらえるように、細心の注意を払いながら伝えることが求められます。
それでは早速見ていきましょう。
配置転換の理由の伝え方
配置転換を行うにあたり、異動となる社員に伝える「配置転換の理由」は極めて重要です。
ここでは配置転換を行う理由を、当事者に伝えるときのコツを3つご紹介します。
配置転換の理由を伝えるときのコツ
- 配置転換の正当性を示す
- 配置転換の妥当性を示す
- 配置転換の期待感を示す
それではひとつずつ見ていきましょう。


正当性を示す
配置転換の理由を伝えるときのポイント、ひとつ目は「配置転換の正当性を示す」です。
配置転換の理由を伝える際は、今回の配置転換が、会社や社員にとって正しい選択であることを示す必要があります。
まずは会社が置かれている現状を正直に伝え、将来のビジョンや社長の考え、配置転換の目的やねらいなどを丁寧に説明し、その上で、今回の配置転換がベストの選択であることを伝えるのです。
そうすることによって、
なぜこのような配置転換が行われるのか?
を知っていただくことができます。
妥当性を示す
配置転換の理由を伝えるときのポイント、2つ目は「配置転換の妥当性を示す」です。
配置転換の正当性を伝えたならば、次のステップは、今回の人選が妥当であることを伝えます。
- 自身のパーソナリティが、新しい職場でどのような役割を果たすのか?
- これまでの経験や仕事ぶりが、新天地でどのように活かせるのか?
- これまで習得した知識やスキルが、どういう場面で必要となるのか?
それらを具体的に伝えるのです。
そうすることによって、
なぜ自分が選ばれたのか?
を理解していただくことができます。
期待感を示す
配置転換の理由を伝えるときのポイント、3つ目は「配置転換の期待感を示す」です。
配置転換の正当性と妥当性を伝えたら、最後に、今回の配置転換への期待を率直に伝えます。
「あなたならきっとやり遂げる」
「あなたなら安心して任せられる」
「あなたを信頼している」
本心から発するメッセージであれば、そんな言葉をかけられて嬉しくない人はいません。
暖かい言葉をかけることによって、
今回の配置転換を、前向きに捉えていただくことができるでしょう。
不当な配置転換をチェック
「不当な配置転換に当たらないか?(該当しないか?)」
を見分けるためのチェックリストをご用意しました。
配置転換を行う場合、基本的には本人の同意を得ることが大前提となりますが、就業規則や雇用契約書に基づいて行う限り、企業は従業員の意思に関係なく配置転換を実施できます。
しかし、場合によっては違法と判断されるケースもありますので、配置転換を決定する前に、以下のチェックリストをご活用いただければ幸いです。
不当な配置転換に当たらないか?をチェック
- 就業規則や雇用契約書に明記されているか?
- 正当性や妥当性、業務上の必要性はあるか?
- 従業員に著しい不利益が生じることはないか?
※こちらのチェックリストは「一般的に不当であると判断される配置転換」を見分けるための、あくまで簡易的なチェック項目となっております。そのため、最終的なご判断は個々の会社にて行っていただきますようお願いいたします。
それではひとつずつ簡単に解説します。
就業規則に書いてある?
不当な配置転換と判断されないために、勤務地の変更・部署間の異動・職種の変更の可能性があることを、就業規則や雇用契約書に明記しているかどうか?を確認しましょう。
記載していない場合や、内容が限定的である場合は、配置転換が無効になることがあります。
業務上の必要性はある?
不当な配置転換と判断されないために、配置転換の正当性はあるか?妥当性はあるか?業務上の必要性はあるか?を明文化できるくらいにしておきましょう。
従業員の能力開花や人材育成、モチベーションの向上や組織の活性化など、明確な目的があれば問題ありません。
従業員に不利益はない?
不当な配置転換と判断されないために、従業員の家庭環境をはじめ、体調や精神的負担などを十分に配慮しているか?をあらためて確認しておきましょう。
従業員があえて会社に報告していない事実があるかもしれませんから、まずは従業員の家庭環境を把握することが重要です。
まとめ
今回は、「配置転換の理由の伝え方」と「不当な配置転換を見分けるポイント」について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、もう一度おさらいしておきましょう。
配置転換の理由を伝えるときのコツ
- 配置転換の正当性を示す
- 配置転換の妥当性を示す
- 配置転換の期待感を示す
不当な配置転換に当たらないか?をチェック
- 就業規則や雇用契約書に明記されているか?
- 正当性や妥当性、業務上の必要性はあるか?
- 従業員に著しい不利益が生じることはないか?
配置転換は「今の場所では本来の力が発揮できない」と判断された従業員を、職場環境を変えることによって、本人のモチベーションを上げたり、パフォーマンスを引き出す試みです。
つまり、「結果が出ない=能力の限界」ではありません。
たとえどのような人材であっても、得意なことはありますし、その人にしかできないことや、その人に適した役割が必ずあります。
上司の仕事は、部下の得意なことを見抜き、適切に仕事を振り分け、人材という貴重な資源を有効活用し、費用対効果を高めることに他なりません。
部下を持つ上司の皆様は、
「従業員の能力が発揮できないのは私の責任だ」
くらいの意識を持って、社員の強みや弱み、得手不得手などを把握することに努めていただきたいと思います。
そして、強みが活かせて弱みをカバーできる環境を用意し、得意なことや興味があることを課題に据えることで、仕事に対する意欲を芽生えさせ、結果が出るまで粘り強く支援してあげてください。
その努力を惜しまなければ、きっと部下は応えてくれると思いますし、仮にそれがうまく機能しなかったとしても、心から部下をサポートする気持ちがあったなら、その思いは必ず伝わります。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました (^.^)
以下、この記事を読んでくださった方へ「オススメの記事」をピックアップしましたので、お時間がございましたらぜひご一読くださいませ。