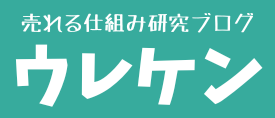「決断力がある人になりたい」
「決断力がない自分に嫌気がさしている…」
「決断力をつけるにはどうすればいいか?」
というあなたに、今回は、
- 決断力を鍛える5つのステップ
- 決断力を高める5つの方法
をご紹介いたします。
「将棋を指すうえで、1番の決め手になるのは何か?」
と問われれば、私は、「決断力」と答えるであろう。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
将棋界で初めて全7タイトル(竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖)を独占した後、2017年に初の永世七冠を達成し、国民栄誉賞の受賞者でもある羽生善治(はぶ よしはる)氏も、著書において「決断力」の重要性を語っておられます。
あらためまして、
「決断する」ということは、「自分で決める」ことに他なりません。
そして、大げさではなく、自分の人生を生きるためには、決断する力、すなわち「決断力」を身につけることが求められます。
では、
決断力を鍛える方法や身につける方法、あるいは、正しい決断を下す方法はあるのか?
結論から申し上げると、決断力を鍛えることや、決断力を高めることは可能です。
ただし、決断力を鍛えるためには、少々周りくどいように思うかもしれませんが、まずはじめに決断することに対する考え方や捉え方を変えてから、決断することに慣れる必要があります。
さらに、決断力を高めるには、これまでとは違った視点から物事を眺めて、正しい決断を下すための「癖づけ」が必要です。
経営者はもちろん、経営幹部や管理職、プロジェクトのリーダーや開発責任者の方は、決断することが仕事と言っても過言ではありません。
ビジネスだけでなく、個人においても、結婚や離婚、引越しや住宅の購入、就職や退職、転職や起業など、誰しも人生において大きな決断を迫られる場面が1度や2度は訪れます。
そんな時、決断力があれば歩みを止めることなく自分を信じて前へと進めますし、より正しい決断ができれば、目先の損得に惑わされることなく、長い目で見ると状況を好転させることができます。
それでは早速「決断力を鍛える5つのステップ」「決断力を高める方法」を順に見ていきましょう。
決断力を鍛えるには
決断力を鍛えるにはどうすればいいか?
「決断力を鍛える」とは、「決断する力を身につけること」を意味します。
では、あらためて、
なかなか決断できない人が、決断を下せるようになるには、どうすればいいのか?
決断力を鍛えるには、次の3つの要素をすべて満たす必要があります。
- 決断することに対する「意味付け」を変えてみる
- 決断することに対する抵抗感をできるだけ減らす
- 多くの決断を下すことで、決断することに慣れる
この3つの要素を満たすことなく、決断力を身につけることはできません。
以下にご紹介する「決断力を鍛える5つのステップ」は、上記の要素をすべて満たすための、具体的なプロセスとなります。
決断力を鍛える5つのステップ
- 目の前の出来事を、ただあるがままに受け止める
- 決断した後の経験や成長を、自分への投資と考える
- 成功者の自伝を読んで、失敗に対する抵抗を減らす
- うまくいかなかった場合の対応を、先に考えておく
- 失敗のリスクも計算に入れて、積極的に行動する
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
ものごとを「良い悪い」と判断しない
決断力を鍛える5つのステップ、ひとつ目は
「目の前の出来事を、ただあるがままに受け止める」
です。
「決断することで、今よりも状況が悪くなるかもしれない…」
決断できない人の多くは、状況が悪化することを怖れ、現状維持を貫こうとするあまり、なかなか決断しようとしません。
そのため、決断する以前に「変化を受け入れる姿勢」が求められます。
あらゆる状況の変化を受け入れるためには、目に前に起こる出来事に対して、一喜一憂しない、つまり、「ものごとをあるがまま受け入れる」ことが大切です。
「これは好き、あれは嫌い」
「これは良い、あれは悪い」
「これは正しい、あれは間違い」
といった見方は、目の前の出来事に対して当事者が自己の都合で勝手に判断するものであって、最初から決まっているものでもなければ、誰かが決めたわけでもありません。
自分にとっていいことがあれば、
「ラッキーだな」
「得したな」
「今日はツイてるな」
と、過剰に興奮することなく自然に受け止めればいいし、困ったことが起きれば
「ま、そういうこともあるさ」
「なるほど、そうきたか」
「さて、これからどうするか」
と冷静に受け止めて、今の自分ができる最前のことを、淡々と行えばいいのです。
心配せずとも、大抵のことはなんとかなりますし、よくないことがずっと続くことはありません。
すべての経験は自分への投資と考える
決断力を鍛える5つのステップ、2つ目は
「決断した後の経験や成長を、自分への投資と考える」
です。
前項でお伝えした「ものごとをあるがまま受け止める」ことから、さらに一歩進んで、次は
「決断することは、自分にとって必ずプラスになる」
と好意的に捉えて、「決断すること」に対する考え方をアップデートします。
「決断すること」とは、「自ら変化を起こすこと」に他なりません。
そして、自ら変化を起こすと、今まで経験したことがない出来事が目の前に現れます。
つまり、「決断すること」によって、新たな経験を積むことができるというわけです。
初めて経験することが、最初からうまくいくことは稀ですが、失敗することによってうまくいかない方法がわかり、何度かチャレンジすることによって、次第にうまくいく方法がわかるようになります。
そうなると、同じような出来事が起こっても、瞬時に頭や体が自然と反応して、周りの人から「すごいね!」と言われるほど、うまく対応できるようになるものです。
これを成長と言わずして、なんと呼べばいいでしょう。
上記のことから、「決断すること」は、自分を成長させるためのスイッチを自分で押すことであり、「自分への投資」と言い換えることができます。
成功者も数多くの失敗を経験している
決断力を鍛える5つのステップ、3つ目は
「成功者の自伝を読んで失敗に対する抵抗を減らす」
です。
目の前の出来事をあるがまま受け止め、「決断すること=自分への投資」と考えることができるようになれば、次は、自分の失敗や過ちを許す「寛容さ」を身につけて、「決断すること」に対する抵抗感を減らします。
自分の決断が失敗に終わったとき、あるいは、自分の決断が間違っていたことに気づいたとき、決断することに慣れていない人は、自分を責めたり、決断したことを後悔したり、ときには自暴自棄になったりするものです。
しかし、落ち着いて世の中の出来事を見渡してみると、誤った決断や、決断による大失敗があまりにも多いことに気づかされます。
歴史に名を残す偉大な人物や、成功者と呼ばれる人物も例外ではなく、彼ら(彼女ら)が下した決断がすべてうまくいったかというと、決してそのようなことはありません。
偉業を成し遂げた人物や成功者の自伝を読んで、
「どんなに偉い人、どんなにすごい人でも決断を誤ることがある」
と理解できれば、
「あんなに偉い人やスゴい人でも決断を間違うことがあるのだから、自分が間違った決断を下しても何ら不思議ではない」
と思えるようになります。
そして、誤った決断や、決断による失敗を何度か経験するうちに、そんな自分を少しずつ許せるようになって、「決断すること」に対する抵抗も少しずつ取り除かれていきます。
最悪の事態を想定し、事前に準備する
決断力を鍛える5つのステップ、4つ目は
「うまくいかなかった場合の対応を先に考えておく」
です。
目の前の出来事をあるがまま受け止め、「決断すること=自分への投資」と考えることができるようになり、さらに「決断すること」に対する抵抗感を減らすことができれば、次は、決断する準備を整えましょう。
決断する準備とは、
「最悪の事態を想定しながら、うまくいかなかった場合の対応を事前に考えておくこと」
です。
決断が良い方に向かう場合を「プランA」とすれば、うまくいかなかった場合を想定した「プランB」や、最悪の事態が起きてしまった場合の「プランC」も用意しておくのです。
実際のところ、最悪の事態が起きることは滅多にありませんから、
「そこまで考えなくてもいいのでは?」
と思われるかもしれませんが、最悪の事態を事前に考えておくことで、少なからず「安心感」を得ることができるのであれば、考えておいて損はありません。
いずれにしても、決断を誤ったからといって、ほとんどの場合は命まで取られることはないので、決断することに慣れてきたら、うまくいかなかったときのプランをいくつか考えておいて、あとは開き直るような気持ちで決断するといいでしょう。
見た目にはかなり危険でも、読み切っていれば怖くはない。
剣豪の勝負でも、お互いの斬り合いで、相手の刀の切っ先が鼻先1センチのところをかすめていっても、読み切っていれば大丈夫だ。
逆に相手に何もさせたくないからと距離を十分に置いていると、相手が鋭く踏み込んできたときに受けに回ってしまう。
逆転を許すことになる。
将棋では、自分から踏み込むことは勝負を決める大きな要素である。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
自分の判断を信じて積極的に行動する
決断力を鍛える5つのステップ、5つ目は
「失敗のリスクも計算に入れて、積極的に行動する」
です。
目の前の出来事をあるがまま受け止め、「決断すること=自分への投資」と考えることができるようになり、「決断すること」に対する抵抗感を減らし、決断がうまくいかなかったときの準備が整ったら、あとは積極的に行動するのみ。
今まで見て見ぬふりをしてきた問題や、判断に迷っていることがあれば、片っ端から決断を下して、ものごとを前へ前へと進めましょう。
- 捨てられないものが溜まっている人は、今の自分に必要なものだけを残して、あとはネットで販売したり、知り合いにあげたり、使えないものは処分する。
- 転職や起業を考えているのであれば、まずは転職サイトに登録して求人情報を閲覧する、あるいは、副業をスタートさせるなど、できることから実行する。
- やりたいことや行きたい場所があるのなら、費用や行き方など必要な情報を収集して、「いつまでに」という具体的なゴールを設定し、すぐに動き出す。
など、決断と行動を繰り返すのです。
そして、いつしか
「決断することが苦にならない」
と思えるようになったとき、あなたは決断力を身につけて、自分で決めた、自分の人生を歩んでいることでしょう。
決断力を高める方法
正しい決断を下すためにはどうすればいいのか?
そんな素朴な疑問にお答えするために、決断力を高める具体的な方法を解説します。
「決断力を高める方法」とは、言わば、「より正しい決断を下す方法」です。
あるいは、「より正しい決断を下すための心得」、または、「正しい決断を下すための考え方」と言い換えることもできるでしょう。
なお、 ここで言う「正しい決断」とは、自分だけにメリットをもたらす決断や、自分が犠牲になることで周りにプラスの影響を与える決断ではなく、自分も含め、周りの人や世の中が少しでもハッピーになるような決断を意味します。
これからご紹介する「決断力を高める方法」は全部で5種類。
ひとつでも多く実践していただいた方が、より正しい決断を下すことができます。
決断力を高める5つの方法
- 目先の損得よりも、長期的な視点で考える
- 人々の幸福や、社会貢献につながるように
- 道徳心を養い、ものごとの本質を見極める
- 体調を万全に整えて、思考をクリアに保つ
- 直感に従い、自分自身で考えて結論を出す
それではひとつずつ見ていきましょう。
長期的な視点を
決断力を高める方法、ひとつ目は
「目先の損得よりも、長期的かつ俯瞰的な視点を持って考える」
です。
目先の利益や快楽、短期的な成功だけに囚われると、一時は喜びを手にすることができるかもしれませんが、周りの状況も常に変化していますから、継続的に利益を出したり、ずっとうまくいくことはまずありません。
正しい決断を下すためには、現状を正確に把握するとともに、数ヶ月後や数年後、数十年後の未来を見据え、長期的かつ俯瞰的な視点を持って、今考えられる最善の選択をする必要があります。
もちろん、長期的かつ俯瞰的な視点から下した決断が、一時的に悪い結果を招いてしまったり、なかなかうまくいかないこともあるでしょう。
しかし、正しい決断をしていたなら、時間が経つにつれて状況が少しずつ改善され、いつしか
「この決断は正しかった」
と思える時が必ずやって来ます。
急がず、焦らず、じっくりと「その時」を待つ忍耐力も、正しい決断には必要なのです。
勝負に勝つことは、企業でいえば目先の利益である。
目先の利益も大事だが、先行投資的な研究もしなければならない。
長く将棋を続けていくには、目先の勝負以外のところで何かしなければならないのだ。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
何らかの経営判断を下すとき、私は「20年後から見ても、自分の考え方は正しかったと言えるだろうか」と確認します。
時間軸を加えることによって、会社の置かれた環境を俯瞰して見つめるためです。
出典:塚越 寛(2019)『末広がりのいい会社をつくる ~人も社会も幸せになる年輪経営~』サンクチュアリ出版.
社会に貢献する
決断力を高める方法、2つ目は
「人々の幸福や、社会貢献につながるような決断を下す」
です。
人間はわがままで自分勝手な生き物ですから、意識しているかどうかにかかわらず、自分の幸せや喜びを優先しがちです。
しかし、先に述べたように、「正しい決断」とは、自分も含め、周りの人や世の中が少しでもハッピーになるような決断を指しますから、決断を下すときは、意識して人々の幸福や、社会貢献につながるような決断を下す必要があります。
人間はわがままで自分勝手な一面を持っていますが、面白いことに、人は誰かに親切にしてあげたり、誰かを援助したり、誰かの活動に貢献すればするほど、幸福感を得ることができます。
つまり、自分ではない誰かのために行う決断こそ、自分が最も幸福を感じる決断であり、正しい決断なのです。
幸福心理学の有名な実験があります。
被験者に、1週間に5つの親切をしてそれを記録してもらいました。
たったそれだけのことで、6週間後には、被験者の幸福度は大きくアップしたのです。
親切を記録するだけで、幸福度はアップする。
なんと、簡単なことでしょう。
出典:樺沢紫苑(2021)『精神科医が見つけた 3つの幸福』株式会社飛鳥新社.
本質を見極める
決断力を高める方法、3つ目は
「日頃から道徳心を養い、ものごとの本質を見極める」
です。
正しい決断を下すには、道徳心を身につけて、ものごとの本質を見極める必要があります。
「そもそもどうしたいのか?」
「本来はどうあるべきか?」
「ほんとうの目的は何なのか?」
上記のような、本質に迫る質問を自分に投げかけ、目の前にある問題を根本的に取り除くために、正しい決断を下す。
その際に、有効な判断軸となるのが「道徳心」というわけです。
道徳心とは、誰もが心の中に持っている「善悪や正邪を判断できる心の中の規範」です。
正しい決断を下す目的が「人々の幸福」や「社会貢献」であるならば、正しい決断を下すためには、より多くの人に受け入れられる考え方や、誰もが理解できる判断軸が必要となります。
世の中には善悪の判断が難しい問題も多々ありますが、「人々の幸福」や「社会貢献」を目的として、道徳心をもって決断するならば、すべての人とまでは言いませんが、大半の人にご理解、ご納得いただけるのではないでしょうか。
心と体を整える
決断力を高める方法、4つ目は
「体調を万全に整え、雑念を追い払って思考をクリアに保つ」
です。
正しい決断を下すためには、決断するときの体調や精神状態も少なからず影響します。
気分が優れない時や疲れている時、別の考え事をしている時や周りがうるさくて集中できない時などは、重要な決断を避けるべきでしょう。
特に睡眠不足や過労、暴飲暴食やお酒を飲みすぎた時は、絶対に決断してはダメ。
朝からいろんな出来事があって、脳が疲れ切っている「夜」に決断するのもオススメできません。
対照的に、一晩ぐっすり眠った翌朝、自然の中で適度に体を動かすことによって脳が目覚め、心も体もリラックスして思考がクリアになり、集中力が高まっている午前中などは、重要な決断を下すには最適と言えます。
正しい決断をするために、十分な睡眠をとって、決まった時間に適量の食事を済ませ、適度に体を動かして、規則正しい生活を心がけましょう。
直感を信じる
決断力を高める方法、最後は
「直感を信じて、心の声に耳をすませ、自ら考えて結論を出す」
です。
直感は単なる「思いつき」ではありません。
直感とは、自分がこれまで経験した出来事をデータベースとして、総合的かつ論理的に導き出された、「自分にとって最適な選択」です。
とはいうものの、
「なかなか直感が働かない…」
という方は、心の声に耳をすませ、粘り強く自分との対話を重ねることで、少しずつ答えが見えてきますから、諦めずに自分に問いかけてみてください。
正しい決断を意識し続けることによって、ある日突然「答え」が見えてきますから、その時が来るまでじっと待ち続けるのです。
それともうひとつ。
人はそれぞれ性格や考え方が異なりますから、どんなに正しい決断を下したとしても、反対する人は必ず出てきます。
とりわけ、直感に頼る決断は、自分でもうまく言葉で説明できない場合があるため、他の人から見れば理解し難いことが多く、多くの人の賛同を得ることは決して簡単ではありません。
そんな時は、
「なぜ自分はこの決断に辿り着いたのか?」
と自分に問うことで、必ず決断に至った理由が明らかになりますから、根気よく自分との対話を続けることが大切です。
私は、人間の持っている優れた資質の一つは、直感力だと思っている。
というのも、これまで公式戦で千局以上の将棋を指してきて、一局の中で、直感によってパッと一目見て「これが一番いいだろう」と閃いたてのほぼ七割は、正しい選択をしている。
将棋では、たくさん手が読めることも大切だが、最初にフォーカスを絞り、「これがよさそうな手だ」と絞り込めることが、最も大事だ。
それは直感力であり、勘である。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
基本は、自分の力で一から考え、自分で結論を出す。
それが必要不可欠であり、前に進む力もそこからしか生まれないと、私は考えている。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
まとめ
今回は
- 決断力を鍛える5つのステップ
- 決断力を高める5つの方法
について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、もう一度おさらいしておきましょう。
決断力を鍛える5つのステップ
- 目の前の出来事を、ただあるがままに受け止める
- 決断した後の経験や成長を、自分への投資と考える
- 成功者の自伝を読んで、失敗に対する抵抗を減らす
- うまくいかなかった場合の対応を、先に考えておく
- 失敗のリスクも計算に入れて、積極的に行動する
決断力を高める5つの方法
- 目先の損得よりも、長期的な視点で考える
- 人々の幸福や、社会貢献につながるように
- 道徳心を養い、ものごとの本質を見極める
- 体調を万全に整えて、思考をクリアに保つ
- 直感に従い、自分自身で考えて結論を出す
自ら決断し、行動した結果を、他の誰かのせいにすることはできません。
当然ながら、うまくいかないことがあっても、自分にとって悪い結果を招いたとしても、すべて真正面から受け止める必要があります。
それが「決断する」ということであり、自分で決めた人生を生きるということ。
自分が下した決断が、すべてうまくいくことはありませんが、たとえ良くないことが起こったとしても、そこから得るものはありますし、必ず次につながります。
どんなに机上で勉強、分析しても、実戦でやってみて「失敗した」「成功した」経験をしないと、理解の度合いが深まらない。
たとえば、1つの場面についての知識や情報をたくさん持っていたとしても、アプローチの仕方とか、理解の仕方とかは深まらない。
理解度が深まらないと、そこから新しい発想やアイデアも思い浮かばない。
いろいろ試したり、実践してみたことこそが、次のステップにつながっていくのである。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
そして、決断とは面白いもので、決断を下した経緯や、決断の内容を見ると、決断を下した人の考え方や価値観が浮き彫りになります。
「この人は、自分の利権しか頭にない」
「この人は、みんなのことを真剣に考えている」
「この人は、今できる最善の決断をしたのではないか」
「この人は、自分の頭で考えて決断していない」
正しい決断を下せる人が、すべて人格者というわけではありませんが、少なくとも、人格者と呼ばれる人は正しい決断が下せるのではないでしょうか。
将棋で大事なのは、判断であり決断である。
私は、決断するときのよりどころは自分の中にあると思っている。
王をとるか、とられるかの厳しい局面では、最終的に自らリスクを負わなければならない。
そういうところでの決断には、その人の本質が出てくるのだ。
出典:羽生善治(2005)『決断力』角川書店.
人格者になれるかどうかは別にして、決断力を高めることで、今よりも正しい決断が下せるようになって、自分も含め、一人でも多くの人が幸せになるような決断をしたいものですね。
最後にもうひとつ。
「日々の業務に追われて、重要な仕事に費やす時間が足りない…」
「経営戦略や人事、新事業について専門分野の人に相談したい…」
という経営者・役員・マネージャーの皆様に画期的なサービスを2つご紹介いたします。
そのサービスとは、
- オンラインアシスタント
- スポットコンサルティング
です。
オンラインアシスタントとは、経理や総務、人事や労務、財務や法務、営業やマーケティングといった様々な分野の専門的な知識やスキル、実務経験を持った外部(社外)の人材が、オンライン上で自社の業務をサポートしてくれる便利なサービスです。
慢性的な人材不足が続き、リモートワークが珍しいものではなくなった今日、月額数万円から依頼できるオンラインアシスタントが、契約社員やパート社員に取って代わる選択肢のひとつとして、あるいは、多忙な経営者やマネージャーの秘書として活躍してくれます。
スポットコンサルティングとは、ピンポイントで知りたい情報やアドバイスしてほしいことを、特定の業界や業務において豊富な経験を持った「その道のプロ」やコンサルタントに、1時間単位で気軽に相談できる便利なサービスです。
こちらのサービスも、意思決定に欠かせない貴重な判断材料(情報)が安価で手に入ることから、経営者のみならず、管理職や事業責任者、商品の開発責任者など、様々なポジションの方に利用されています。
いずれのサービスも、スピード感を持って会社経営を行う上では利用価値が高いサービスなので、少しでも気になる方は是非チェックしてみてくださいね。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)