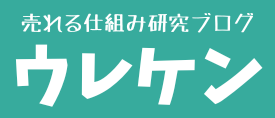「イノベーションを起こすにはどうすればいいか?」
「イノベーションを生み出す組織風土や阻害要因とは?」
「イノベーション創出において、最初にすべきことは?」
というあなたに、今回は、
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?
という大きな問いに対して、
- イノベーションを起こす職場環境
- イノベーションを起こす組織風土
- イノベーションを起こす阻害要因
という、3つの異なる視点から考察するとともに、
イノベーションを生み出す具体的な取り組みとして「まず最初にすべきこと」
について解説いたします。
イノベーションを起こす方法については、さまざまな考え方や切り口があり、イノベーションを起こす人や条件について論じているものもあれば、イノベーションにつながるアイデアを出す手法など、多種多様です。
しかし、どの方法を選んだとしても、必ずイノベーションを起こせるわけではありません。
何かを達成するためには、「これをやると必ずうまくいく」という方法を選ぶよりも、「これをやると必ず失敗する」という方法を避けることの方が、結果として早く達成できます。
そういう意味において、これからご紹介する内容はイノベーションを起こすために必要不可欠な要素であり、これらを抜きにしてイノベーションを起こすことはできません。
加えて、イノベーションは目的やゴールではなく、問題を解決する際の画期的な「手段」であることを踏まえると、イノベーションを起こすには、個性的な考えや独自の視点も必要となります。
では、イノベーションを起こすにはどうすればいいか?何から始めるべきか?
早速見ていきましょう。
イノベーションを起こすには?
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?
大前提として、イノベーションとは目的ではなく、あくまでも「結果」です。
イノベーションは「技術革新」と呼ばれることもありますが、本来の意味は「新たな価値を創造すること」であり、世の中に大きなインパクトを与えた革新的な製品やサービス、ビジネスに多大な影響を及ぼした仕組みや方法です。
つまり、
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?
を要約すると、
世の中に大きなインパクトを与えるほどの革新的な製品やサービス、ビジネスに多大な影響を及ぼすほどの仕組みや方法を生み出すためにはどうすればいいか?
となります。
その点を踏まえた上で、あらためて
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?
という問いに答えるならば、
イノベーションを起こすには?
- イノベーションが生まれやすい環境を整える
- イノベーションが生まれる組織風土をつくる
- イノベーションの最も大きな阻害要因を知る
となります。
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
イノベーションが生まれる環境
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?ひとつ目は「イノベーションが生まれる環境を整えること」です。
では、イノベーションが生まれる環境とは、一体どのような環境か。
一言で言うと、新たなチャレンジを良しとする環境です。
「職場にチャレンジしやすい空気が流れている」
「新たなチャレンジを推奨し、支援する体制が整っている」
など、チャレンジすることは「良いこと」だとする会社の姿勢が明確に示されている環境こそ、イノベーションが生まれる環境と言えるのではないでしょうか。
イノベーションが生まれやすい会社は、そうでない会社に比べて、ミスに対する姿勢や考え方がまったく異なります。
失敗やミスが起こったとき、失敗やミスを起こした本人だけを責めるような会社では、新しいことに挑戦しようと考える社員は育ちません。
なぜなら、新しいことにチャレンジすると失敗やミスは避けられませんし、慣れきった仕事だけを行う方が失敗する確率は低く、ミスも生まれにくいからです。
対照的に、失敗やミスが起きたとしても、周りの社員がすかさずフォローしてくれる職場は、精神的なプレッシャーも少ないため、失敗やミスを引きずることもありませんし、社員が安心して目の前の仕事に取り組めますから、結果として新たな提案や挑戦も生まれやすくなります。
そのような会社は、失敗やミスを防止する改善策についても部署単位で考え、ミスが起こらない仕組みを導入するにあたって費用が発生する場合も、会社が渋ることなく積極的に投資する姿勢が見られます。
つまり「イノベーションが生まれる環境」とは、ひとりの失敗やミスも、周りの社員が自分ごとのように捉え、そこに居合わせた人が全員で
どうすれば改善できるか?
どうすればもっと会社が良くなるか?
という視点で物事を考えることができる組織・会社と言えるでしょう。
会社が社員を大切に扱い、社員が顧客を大切に思い、顧客が気持ちよく会社の商品やサービスを利用する…そんな好循環が社員のチャレンジ精神を育み、そこから生まれた新たな商品やサービスがイノベーションを起こすのです。
イノベーションというのは花のようなもので、それ自体を人為的に生み出すことはできないのです。
我々ができるのは、花が育ちやすい土壌と環境を整えて十分に栄養と日光を注いでやることだけです。
出典:山口周(2017)『知的戦闘力を高める独学の技法』ダイヤモンド社 .
イノベーションを起こす組織の条件
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?2つ目は「イノベーションが生まれる組織風土を作ること」です。
では、イノベーションが生まれる組織風土とは、一体どのようなものか?
組織風土とは、組織に属する人間が持っている考え方や価値観のことで、今まで組織を構成していた人たちの価値観や考え方が大きく影響、反映されます。
では、イノベーションを起こすために必要な考え方や価値観とは何か?
それは、誤解を恐れず言うならば、
「ミスの削減よりも、顧客ニーズに応えることを重視する」
といった考え方や価値観です。
だからといって、決してミスの削減を軽視しているわけではありません。
ミスを削減する、あるいはミスが根本的に起こらないようにすることは重要かつ必須です。
しかしながら、ミスの頻度が極めて少なく、ミスが起こっても迅速にリカバリーできるような体制を整えているのであれば、過度にミスをゼロにする対策を行うよりも、より多くの顧客ニーズに応えることを中心に据えた活動を重視すべきでしょう。
ミスの削減や、ミス撲滅を部署の目標に掲げている会社も見受けられますが、目標設定にまで「ミスの削減」が登場すると、社員は
「誰のために仕事をしているのか?」
「何のために働いているのか?」
と考えてしまい、仕事の意味を見失ってしまいます。
そして、ミスの削減を目標に据える最も大きなは弊害は、社員のチャレンジ精神が奪われることです。
「ミスをしてはいけない」
「ミスをすると評価が下がる」
「ミスをなくすことが重要」
という考え方や価値観が浸透すると、そこで働く社員は極度にリスクを嫌い、失敗やミスを避けようとするあまり、与えられた仕事だけをこなすようになります。
ただただミスをしないように気をつけて、ミスが起きてしまったら自分を責める…そんな職場から新たなチャレンジが生まれるはずもなく、創造力を発揮することもなければ、技術が進歩することもありません。
それだけならまだしも、自分が起こしてしまった失敗やミスを上司から激しく叱責されたり、それによって大きく評価が下がるようなことがあれば、失敗やミスを隠そうとする社員も現れます。
それが大きくなると会社内で偽装や隠蔽が行われるようになり、世間を騒がすような会社の不祥事に繋がるなど、イノベーションを起こすどころか、会社の存続さえ危ぶまれる事態に発展しかねません。
致命的なミスは回避しなければなりませんし、ミスを削減することも大切ですが、新たな価値を創造することに社員の意識を向けさせるような組織風土が根付かなければ、いつまで経ってもイノベーションを起こすことはできないでしょう。
組織風土はこれまで培ってきた組織の伝統や取り組み方、古くから在籍している従業員の言動が元となっていますから、簡単に変えることはできないかもしれません。
しかし、小さなチャレンジを繰り返して、小さな成功を積み重ねていくことで、ひとり、またひとり、と周りの人間を巻き込みながら、少しずつではありますが、変えていくことは可能です。
そして、新たなチャレンジが珍しいことではなくなった時、「イノベーションが生まれる組織の条件は整った」と言えるでしょう。


イノベーションの阻害要因
イノベーションを起こすにはどうすればいいか?3つ目は「イノベーションの阻害要因を取り除くこと」です。
では、イノベーションの阻害要因とは何か?
イノベーションを起こす環境が整い、組織風土が変わることによって、チャレンジ精神を持った社員が増え、社内で新たな取り組みに挑戦する動きや、既存の仕組みを改善する活動が活発化します。
そうなれば「イノベーションが起きるのも時間の問題」…と思いきや、実はもうひとつ、超えなければならない大きな壁が目の前に立ちはだかります。
その大きな壁とは、「みんなの意見」です。
つまり「みんながいいと思うものに流されてしまう」、
あるいは「何事も多数決で物事を決める」ことです。
「みんなの意見」は、イノベーションを起こす上で、最も大きな阻害要因と言っても過言ではありません。
誰もが「いいね」と称賛するアイデアは、成功する確率が低い
上記は私が新しい商品やサービス、仕組みや方法を考えるときに教訓としていることです。
「みんながいい」と思うものは安全でリスクが低く、誰もが簡単に思いつくアイデアと言えますから、「みんながいい」と思うアイデアを実行したところで、イノベーションを起こすことはできません。
そもそもイノベーションを起こすような商品やサービスなどは、アイデア段階では「実現が不可能ではないか?」と酷評されたり、「本当に需要があるの?」と疑問視されることが多く、革新的な商品やサービスは、それらの批判や疑いを乗り越えた先にあるものです。
例えば、今でこそ当たり前のように利用している「クロネコヤマトの宅急便」は、個人宅への配達を郵便局が独占していた時代に、ヤマト運輸が業績を立て直すための施策として始めたサービスですが、スタートするまでは採算が合わないとして役員から猛反対を受けていました。
ネットショップのAmazonも1999年末から2000年末にかけて、物流センターへの投資によって巨額の赤字を続け、株価は大幅に下落し、倒産するのは時間の問題という見方もありましたが、大方の予想を裏切り、結果としてIT技術とリアルな物流センターの融合によって復活を果たし、世界最高水準の在庫回転率を誇るネットショップの王様として今もなお君臨しています。
上記の会社は、いずれも多くの人の理解を得られない、まさに逆風の中を進むことになりましたが、アイデアを考えた人の頭の中には明確なビジョンが既にあり、理論的にも実現可能であることがわかっていて、必ず実現できるという確信を持っていたのでしょう。
強い信念と揺るぎない自信がなければできないことだとは思いますが、彼らのチャレンジ精神のおかげで私たちは新たな価値を享受し、その恩恵を受けていることを考えると、心から感謝しなければなりません。
イノベーション創出の取り組み
イノベーション創出の取り組みとして、最初にすべきことは何か?
イノベーションを生み出す環境を整えることや、イノベーションが生まれやすい組織風土を根付かせることも大切ですが、イノベーションを生み出す具体的な取り組みとして、最初にすべきことは、
「理由なき同調を排除して、全員一致を疑う視点を持つこと」
です。
イノベーションを生み出す方法や仕組み、イノベーションを生み出す人や組織の作り方を論じる方もいらっしゃいますが、それらの方法や仕組み、人や組織は多種多様であり、一律に同じやり方を当てはめようとしても再現性が乏しく、大抵はうまくいきません。
イノベーションは課題や問題を解決する際の「画期的な手段」であり、その方法は人によって異なりますし、それぞれの会社によって組織の作り方も異なります。
ではなぜ、「理由なき同調を排除して、全員一致を疑う視点を持つこと」が、イノベーションを創出する最初の取り組みとして最適と言えるのか?
詳しくみていきましょう。
理由なき同調が会社を蝕む
同調とは他人の意見や主張に賛同し、同じ態度や行動をとることを言いますから、「理由なき同調」は、「理由もないのに同調すること」という意味になります。
つまり「理由なき同調」とは、自ら考えることを放棄して、心から賛成しているわけでもなければ反対しているわけでもなく、(周りの空気を読んで)他人の意見や主張に賛同し、同じ態度や行動をとることを意味します。
では、会議やミーティングで「理由なき同調」が常態化するとどうなるか?
積極的に自分の意見を口にする人がいなくなり、上司の顔色を見ながら発言する人が増え、斬新な考えや画期的なアイデアも生まれなくなることは想像に難くありません。
イノベーションを生み出すためには、これまでの常識や前例を疑い、積極的に変化を受け入れ、未来に向けて新たな一歩を踏み出す行動力が求められますから、「理由なき同調」が大きな障害となることは明白です。
では、なぜ「理由なき同調」が生まれるのか?
どうすれば会議やミーティングの場において「理由なき同調」を無くし、自由闊達な意見交換や、会社の未来を切り開くような提案が生まれる雰囲気を作り出すことができるのか?
まずは「理由なき同調」が生まれる原因について考えてみましょう。
理由なき同調が生まれる原因
「理由なき同調」が生まれる原因は何か?
断定はできませんが、過去から脈々と受け継がれている「組織風土」をはじめ、幹部や役職者、長く勤めている社員の考え方や価値観が大きく影響していると想像します。
「理由なき同調」が常態化するということは、「社員が考えることを放棄している」状態です。
「考えることが苦手」なのか、「考えても意味がない」と思っているのか、あるいは「考えなくてもいい」と思っているのか、理由はいろいろあるでしょうが、いずれにしても、そのような状況を生み出している原因を探り、取り除く必要があります。
誰もが「これはおかしい」と思っていることが放置され、誰もが不便に感じている方法がいつまでたっても改善されない…みなさんもそんな経験が1度や2度はあるのではないでしょうか。
残念ながら、私もそんな現実を目の当たりにした経験があります。
良かれと思って提案しても、
「以前もそうだったから」
「また考えておきます」
など、意味のわからない理由をつけて却下され、改善に取り組む素振りすらなく、場合によっては逆ギレされることも…辛かったというより、当時は「面食らった」というのが正直なところです。
何度かそんな経験をすると、
「この人たちには何を言っても変わらない」
と思うようになり、私の場合、最終的には
「自分の権限で変えることができる範囲だけでも少しずつ変えて行こう」
という考え方にシフトしていきました。
今思うとそれが正しい方法だったのか疑問に感じる部分もありますし、別の方法もあったのかもしれませんが、その時の自分はそれが精一杯だったのでしょう。(まだ若かったですし)
私は「考えること」が好きだったので、上司に却下されても自分のできる範囲で勝手にちょこまかと動いていましたが、「考えることが苦手」な社員が上記のような経験をすると、大半の人は
「自分が考えても意味がない」
「提案するだけ時間の無駄」
「周りの先輩や上司に合わせよう」
と思うでしょう。
本来は社員を教育することで、社員の成長とともに会社も成長しなければならないのですが、これでは成長どころか衰退の一途を辿ります。
では、「理由なき同調」を排除するためにはどうすればいいか?
全員一致を疑う視点を持つ
「理由なき同調」を排除するために、まずは「全員一致を疑う」ことです。
「誰もが賛成すること」は「誰もが知っていること」である場合が多く、「誰もが知っていること」は既に「他の誰かが行っていること」が大半です。
そのため、すんなりと全員一致するような意見や考えの中に、斬新なアイデアや画期的な考えは1ミリたりとも存在しないと思った方がいいでしょう。
ではどうすればいいか?
まずは社長や幹部社員が
「安易な全員一致を良しとしない」
と肝に銘じ、全員一致を疑う視点を持つことから始めるのです。
社長や幹部社員が中心となって「全員一致を良しとしない」とする方向に舵を切り始めると、ありきたりな意見よりも個性的な意見が重宝されます。
これまで考えることを放棄していた社員も「理由なき同調」を続けることができなくなり、必然的に全ての社員が自分の頭で物事を深く考えなければならなくなるでしょう。
自分の頭で考えることに対して、プレッシャーを感じる社員も出てくるでしょうが、これまで自分の頭で考えることをしないまま、コンフォートゾーンで快適に仕事をしていた社員にはちょうどいい刺激になります。
自分の頭で考える社員が増えて、しばらくすると好循環が生まれます。
これまで当たり前のように行っていた仕事に疑問を持つようになったり、社員間のコミュニケーションが増えたり、業務の見直しや商品のリニューアル、サービスの改善などが活発に行われるなど、少しずつ会社の雰囲気が良い方向に変わることを実感できるでしょう。
そして、自分の頭で考える社員が増えると、イノベーションが生まれる可能性が飛躍的に高まります。
個性的な考えや斬新な発想を発言しやすい環境が生まれることで、自分だけが持っているものを表現する機会が与えられ、自分にしかできないことを実行に移す可能性が開けると、これまで思いもつかなかった画期的な商品やサービス、仕組みや方法が現実のものとなります。
その中から、イノベーションと称されるものが誕生しても、何ら不思議ではありません。
まとめ
今回は、イノベーションを起こす環境や組織の条件、阻害要因や創出する際の取り組みについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、
もう一度「イノベーションを起こすにはどうすればいいか?」を確認しておきましょう。
イノベーションを起こすには?
- イノベーションが生まれやすい環境を整える
- イノベーションが生まれる組織風土をつくる
- イノベーションの最も大きな阻害要因を知る
私自身、これまで多くの商品やサービスをプロデュースしてまいりました。
それらの商品やサービスが、すべて「イノベーションを起こせたか?」と言われると、残念ながら、大きな声で「もちろん!」と答えることはできません。
しかし、世の中に大きなインパクトを与えることはできませんでしたが、限られた業界や競合他社の間で噂になるくらいのインパクトなら、何度か与えた経験があります。
その時のことをあらためて思い出してみると、やはり
- 新たなチャレンジをどんどん推奨する職場環境
- 前向きな行動によるミスを許容してくれる組織風土
があったように感じます。
あとは、良くも悪くも、私自身が周りの意見に耳を傾けながらも、自分の直感を信じて突き進むタイプだったので、イノベーションの阻害要因とされる「みんなの意見」は右から左に流していました…。
そのため、一部の人たちから向かい風をまともに受けることもありましたが、結果を出すことで、少しずつ周りの理解が得られるようになったと記憶しています。
今となっては、もう少し別のやり方があったかも…と思うことも多々ありますが…。
イノベーションを創出する上では、まず初めに「影響力が高い人」から変わらなければなりません。
つまり、社長や幹部、役職者や先輩社員です。
まずは先を歩く人間が、前例を作ること。
言葉にするのは簡単ですが、実際に勇気を持って実行することは容易ではありません。
ここでご紹介した方法以外にも、イノベーションを生み出すための取り組みはいろいろあるでしょうが、詰まるところ、これまでのやり方や常識を疑って、別の視点からゼロベースで考えることが習慣にならなければ、いつまで経っても変化は起きないでしょう。
「全員一致を疑う」という視点は、「考えること」を社員に求めるきっかけとなり、会社が変わる分岐点となり得ます。
いろんな情報が簡単かつ瞬時に手に入るようになった今日、情報の価値が下がっている時代だからこそ、深く考えた先にある個性的なアイデアの価値は高く、貴重です。
これまでの常識を覆すような商品や、盲点を突いた画期的なサービスは、天才と呼ばれる一部の才能ある人間だけが生み出すことができると思われがちですが、そんなことはありません。
彼や彼女らと同じくらい深く、そして粘り強く考え抜くことができれば、私たちにもそこそこ画期的な商品やサービスは生み出せる…はず。
そのために会社がすべきことは、ひとりひとりの社員が自分の頭で考えるための土壌を作ること。
それができれば、あとは社員を信じるのみ。
イノベーションを起こすには、シンプルにそれだけでいいのかもしれませんね。
最後にもうひとつ。
「日々の業務に追われて、重要な仕事に費やす時間が足りない…」
「経営戦略や人事、新事業について専門分野の人に相談したい…」
という経営者・役員・マネージャーの皆様に画期的なサービスを2つご紹介いたします。
そのサービスとは、
- オンラインアシスタント
- スポットコンサルティング
です。
オンラインアシスタントとは、経理や総務、人事や労務、財務や法務、営業やマーケティングといった様々な分野の専門的な知識やスキル、実務経験を持った外部(社外)の人材が、オンライン上で自社の業務をサポートしてくれる便利なサービスです。
慢性的な人材不足が続き、リモートワークが珍しいものではなくなった今日、月額数万円から依頼できるオンラインアシスタントが、契約社員やパート社員に取って代わる選択肢のひとつとして、あるいは、多忙な経営者やマネージャーの秘書として活躍してくれます。
スポットコンサルティングとは、ピンポイントで知りたい情報やアドバイスしてほしいことを、特定の業界や業務において豊富な経験を持った「その道のプロ」やコンサルタントに、1時間単位で気軽に相談できる便利なサービスです。
こちらのサービスも、意思決定に欠かせない貴重な判断材料(情報)が安価で手に入ることから、経営者のみならず、管理職や事業責任者、商品の開発責任者など、様々なポジションの方に利用されています。
いずれのサービスも、スピード感を持って会社経営を行う上では利用価値が高いサービスなので、少しでも気になる方は是非チェックしてみてくださいね。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)