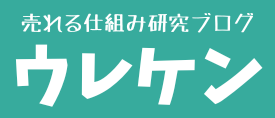「中小企業が生き残るための戦略とは?」
「中小企業が商品開発を行う際のポイントは?」
「中小企業はリスクとどう向き合えばいいか?」
というあなたに、今回は
- 中小企業の生き残り戦略
- 中小企業における商品開発の意味
- 中小企業のリスクヘッジの考え方
について解説いたします。
結論から申し上げると、中小企業が生き残るためには商品開発が欠かせません。
しかしながら、新商品を出せば必ず売れるわけではありませんから、商品開発を任された社員は責任重大です。
かといって、商品開発に着手しないまま、既存の商品だけに頼っていては現状維持が精一杯ですし、何もしなければ売上は右肩下がり…でも商品開発はリスクが高い…ほんとうに悩ましいですよね。
では、中小企業はリスクをどのようにして避けたらいいのか?
「リスクヘッジ」とは、起こりうるリスクを予測して、リスクに対応できる体制を整えることを言いますが、ここでひとつ素朴な疑問が浮かび上がります。
「そもそも、起こりうるリスクを予測することはできるのか?」
ということです。
仮にリスクを予測できたとして、
それがいつどのようなタイミングで起こるのか?
リスクに対する備えにどれくらいの時間と労力を費やせばいいのか?
考えれば考えるほど、分からなくなりますよね。
とりわけ、中小企業や小さな会社は本業に忙しく、それ以外の時間を最小限に抑えたいとお考えでしょうから、リスクヘッジに多くの時間とお金を費やすことはできません。
では、不確定要素が多い「リスク」と、中小企業はどのように向き合うべきか?
今回の記事では、商品開発を軸に置いた生き残り戦略をはじめ、商品開発を成功に導くためのポイントや商品開発を行うメリットをお伝えするとともに、中小企業がとるべきリスクヘッジの考え方についてわかりやすく解説いたしますので、業績が伸び悩んでいる中小企業の経営者やマネージャーの方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
それでは早速見ていきましょう。
中小企業が生き残るためには
小さい会社や中小企業が生き残るためにはどうすればいいか?
結論から申し上げましょう。
中小企業の生き残り戦略は、ズバリ「自社商品の開発」にあります。
すでに自社のオリジナル商品を販売している場合は、新商品や新サービスを定期的に生み出すことが、中小企業における生き残り戦略になり得ます。
自社商品を開発することが、なぜ中小企業の生き残り戦略につながるのか?
それは、
- 自社商品を開発することで、独自のノウハウを蓄積できる
- 自社商品の開発を経験することで、本物の人材を育成できる
- 自社商品を開発すること自体が、会社の危機管理に直結する
からです。
もちろん、中小企業の生き残り戦略が自社商品の開発だけというわけではありませんが、今日の予測不可能な時代にあって、既存の事業や商品に頼るばかりでは、企業の継続的な成長は望めません。
それでは、自社商品の開発が中小企業の生き残り戦略につながる理由について、ひとつずつ詳しくみていきましょう。
ノウハウを蓄積できる
中小企業が生き残るためには、自社で培った「自社独自のノウハウ」が欠かせません。
「商品開発=新たなチャレンジ」は、言うなれば未知の世界への扉を開くことを意味します。
日常の業務に慣れきってしまうと毎日の仕事が「作業」に変わり、それ以上のことを考えたり、提案したり、積極的に行動することがいつしか億劫になってしまい、「現状維持=心地よい状態」から抜け出せなくなります。
たいていの人は変化を嫌いますから、自ら率先して行動する一部の社員を除いて、定期的に環境を変えてあげることが必要です。
そういう意味において、新商品や新サービスを開発するというミッションは、まさに「うってつけ」。
心地良い状態から抜け出す良いきっかけになることはもちろん、日々「目的を達成しなければならない!」という指令が脳内を刺激し続けますから、能動的に動かざるをえません。
するとどうなるか?
「もっといい方法はないか?」
「もっと美しいデザインにできないか?」
「もっと便利にするためにはどうすればいいか?」
と自分の頭で考えながら、いろんな方法を試して行動を積み重ねるうちに、時間はかかるかもしれませんが、自然と上手なやり方やコツがつかめるようになってきます。
そこで生み出された独自の方法やコツが抽象化されて、ひとつにカタチになる時、「ノウハウ」と呼ばれるものが誕生します。
仕事に限って言うと、
ノウハウとは「特定の仕事をスムーズに行うための知識や技術、方法や手順、コツや考え方」です。
ノウハウを習得するには、今まで経験したことがない新たな課題を設定して、その課題をクリアするために試行錯誤しながら行動し続けるしか方法はありません。
すなわち自社商品を開発することが、新たなノウハウを獲得し、蓄積することにつながるのです。
くどいようですが、それ以外の方法でノウハウを身につけることはできません。
たとえ開発した商品やサービスが全く売れず(利用されず)、あるいは鳴かず飛ばずに終わったとしても、その経験を通して得たノウハウは必ず次の商品開発に活かされます。
そしてこの「ノウハウの蓄積」こそが、中小企業が生き残るために必要なのです。
今売れている商品やサービスも、何かのきっかけでいつ売れなくなってしまうかわかりません。
そんな時、これまで蓄積してきた自社独自のノウハウがあれば、ゼロから商品やサービスを開発するよりも、短い期間で商品を開発したり、ノウハウ自体が商品となることもあります。
ノウハウは使えば使うほど磨きがかかり、ご存知の方も多いと思いますが、「トヨタ生産方式」みたいな独自の仕組みが出来上がることもあります。
もし私が「どうすればヒット商品を生み出せるか?」
という質問をされたら、適切な答えを見つけることはできませんが、
「どうすれば中小企業が生き残ることができるか?」
という質問に対しては、
「できるだけ多くの経験を積み重ねてノウハウを蓄積すること」と即座に答えるでしょう。
本物の人材を育成できる
中小企業が生き残るためには、自社商品の開発を行うことによる「本物の人材育成」が欠かせません。
自社商品の開発は、メンバーの潜在能力を引き出す大きなきっかけとなります。
潜在能力とは「既に持っているけど表に現れていない能力」であり、潜在能力を引き出すためには、本人が自分の持っている能力に「気づく」必要があります。
そして、日々の業務の中では、自分の中に埋もれている能力に「気づく」ことはできません。
社長や幹部の間で「社員を育てる」という話になると、「〇〇人材育成プログラム」「〇〇人材教育システム」といった仕組みを導入しようとする動きが起こります。
講師を会社に招いてセミナーを受講させたり、1泊2日の研修に参加させるなど、すぐに外部の会社に頼ろうとする傾向があるようです。
そのほうが手っ取り早いですし、とりあえず「やった気になる」のでしょう。
社長や幹部のお気持ちはとても理解できますし、一定の効果はあるのかもしれませんが、人間はそう簡単に変われる生き物ではありません。
ためになる本を何冊読んでも、行動に移さなければ意味がないのと同じ。
実際に行動して壁にぶち当たり、その度に自分の頭で考え、失敗や成功を繰り返しながら少しずつ自信が持てるようになり、気がつけば知識や技術が身についていて、自分の隠れた能力や得意なことがわかってくる…。
少々面倒ですが、このステップを抜きにして社員が成長することはありません。
人はそれぞれ個性があり、性格も違えば価値観も異なります。
そんな人たちに同じ話を聞かせて一律の指導をしたところで、必要最低限のことを教えることはできても、全体的なベースアップを図ることは難しいでしょう。
ましてや個々の潜在能力を開花させるとなれば、なおさらです。
人材育成は必要最低限のマナーなどに止め、そこに予算を投じるのではなく、自社商品の開発を通じて、自分の頭で考えさせる経験を数多く積ませたほうがよっぽど人材育成に繋がります。
あるいは社員の個性を生かしながら「良いところをもっと伸ばす」方向で個別に指導したり、自社商品の開発を通して成功や失敗をメンバーと共に分かちあい、お互いを尊重することで協調性やコミュニケーション能力を育むことこそ、「多様性」が叫ばれる今日の社会に必要な「本物の人材育成」と呼べるのではないでしょうか。
学校教育に例えるとお分かり頂けると思いますが、同じ授業を行っていても、成績優秀な子供と勉強が苦手な子供が生まれるのはなぜでしょう?
できる子はどんどんできるようになり、苦手な子は何かのきっかけがなければ勉強を好きになることもありませんし、もちろん成績が上がることもありません。
人材育成セミナーや人材教育システムを導入するのであれば、
「社員を育てるとはどういうことか?」
「社員にどうなって欲しいのか?」
などを明確にして、過度に期待せず、受講や導入を検討することをオススメいたします。
売上の引き出しを増やせる
中小企業が生き残るためには、自社商品の開発を行うで「売上の引き出しを増やす」ことが重要です。
「ここ数年、売上や客数も減少傾向。何か新しいことを始めなければ…」
「新型ウイルスの流行で、主力商品が軒並み売れなくなってしまった…」
「仕入れ先で災害が起きて原材料を確保できず、商品が生産できない…」
未来を予測できればいいのですが、残念ながら私たちが生きている世界では、時として予測不可能な事態が突然起こります。
VUCA(「ブーカ」と読みます)という言葉をご存知でしょうか?
VUCAとは4つの形容詞の頭文字を合わせた言葉で、Volatile(不安定)、Uncertain(不確実)、Complex(複雑)、Ambiguous(曖昧)の意味を持った、今日の予測不可能な社会を言い表す用語です。
不安定で不確実、複雑で曖昧な今日において中小企業が生き残るためには、あらゆる危機に備えておく必要があります。
言うまでもありませんが、危機は台風や地震といった自然災害だけでなく、リーマンショックのような経済危機、新型ウイルスの流行による未知の病原菌がもたらすパンデミック、仕入先の倒産や社員の不祥事など様々です。
これらの危機は予測することが不可能で、ある程度は個別に対策を講じることはできても、根本的にはその都度対応を迫られることになりますから、「日頃からどう備えるか?」がポイントとなります。
そのためには、何が起きてもある程度の期間は事業が継続できるように、利益を生み出すいろんな「引き出し」を持っておくことが「危機に対する備え」となり、売上の減少を最小限に抑える唯一の方法と言っても過言ではありません。
例えば食品を製造している会社であれば、製造過程で生まれる成分を利用して、化粧品や健康食品を作ったり、食品を加工する過程で廃棄していた成分を有機肥料にするなど、新たな自社商品を開発を模索してみる。
そうすることで、メインの食品が何かの原因で製造することができなくなったとしても、新たに始めた商品の製造は継続できるかもしれません。
会社の倉庫に防災グッズの準備をすることも大切ですが、どんな危機が訪れても会社が事業を継続できるように、新たなチャレンジに投資すること、つまり「継続的に商品開発すること」が会社の危機管理に直結するというわけです。
中小企業における商品開発とは
中小企業にとって、商品開発はどのような意味を持つのか?
一言で申し上げると、中小企業における商品開発とは「投資」です。
ただし、ひとつの銘柄(商品)に巨額の予算を投資してはいけません。
多くの銘柄(商品)に、少しずつ投資することが、商品開発を成功させる上で、大きなポイントとなります。
つまり、「多くの商品を世に出して良いものだけを残す」というスタンスで、良いアイデアをできるだけ早く商品化できる体制を整え、企画から発売までのスパンを短くすることが、多くのヒット商品を生み出すことにつながります。
そして、商品開発という名の投資には、もうひとつの意味があります。
それは、「社員の成長」への投資です。
中小企業が商品開発を行う際は、「社員の成長」に投資するつもりで、「商品開発に一定の人員を割く」ことをオススメします。
例えば、従業員数が30人の会社であれば、その10%にあたる3人を、2,000万円の予算が使えるとすれば、その10%である200万円を商品開発に投資するのです。
ある程度のリスクを覚悟した上で、新商品や新サービスを開発する専門のチームを立ち上げ、一定の予算を預けてチームのメンバーに委ね、可能であれば広告宣伝や販促プロモーションも任せる。
上司は定期的に進捗を確認したり、必要に応じてアドバイスするに止まり、基本的には余計な口出しをせずに、チームのメンバーを信頼して一歩外から見守ります。
なぜそうするのか?
それは、大胆に任せることで、チームに責任感が芽生えるからです。
同じ目標に向かって進むことで、お互いを助け合う気持ちが生まれ、メンバー間で信頼関係が出来上がっていきます。
さらに自分たちの頭で考えることが習慣となり、仕事へのやりがいも今まで以上に強く感じるようになるでしょう。
チーム内では常に活発な意見交換が行われ、誰かが出したアイデアを他の誰かが膨らませるといった相乗効果も期待できます。
チーム内で意見や考えが異なる場合も起こり得るため、あらかじめ会社の経営理念やビジョンに基づいて意思決定を行うリーダーも決めておいたほうが良いでしょう。
「社員の成長」に投資するというスタンスで商品開発を行うならば、それがうまくいっても、うまくいかなくても必ず成果が得られます。
つまり、最終的にリリースした商品やサービスが好調な売れ行きを示せば、大きな達成感が得られることでメンバーが自分の仕事に自信が持てるようになり、仮にうまくいかなかったとしても「何が良くなかったのか?」「どうすればうまくいくのか?」など、メンバー全員が自分ごとのように考えるようになります。
「商品開発に一定の人員や予算を投資する」ということは、新商品や新サービスを生み出すだけでなく、任された社員が大きく成長する機会を与えることにつながります。
そこで育ったメンバーが前回の経験を活かして別のプロジェクトのリーダーとなり、新たなプロジェクトを成功に導く…そんな好循環が生まれると、一定の周期で新商品や新サービスを世に送り出すことができるのではないでしょうか。
最後にチームメンバーの選任について一言付け加えさせてください。
これについてはいろいろな方法があると思います。
各セクション(部署)でプロフェッショナルといえる人材を集め、その中から商品開発メンバーを選出する方法もありますし、まずはじめにプロジェクトリーダーを任命し、そのリーダーが他のメンバーを選ぶという方法もあるでしょう。
いずれにしても
「この人に任せた!」
「このメンバーでだめだったら仕方ない」
と思える人を選ぶようにしなければなりません。
メンバーの選任をするにあたり重視すべきスキルをひとつだけ挙げるとするならば、私は迷わず「コミュニケーション能力」と答えるでしょう。
他のメンバーの意見を尊重したり、お互いを助け合う姿勢は、円滑なコミュニケーションがあって初めて成り立つものです。
個々の弱点は他のメンバーが補うことで解消されますが、コミュニケーション能力に劣るメンバーが一人でもいると、チーム内の雰囲気が悪くなり、お互いに気を使いながら仕事をすることになります。
そんな状況で斬新なサービスや個性的な商品が生まれるはずがありません。
中小企業のリスクヘッジの考え方
中小企業や小さな会社は、積極的にリスクを回避すべきか?
それとも、リスクに備えることなく、何事にも果敢にチャレンジすべきか?
ここでは、そんな中小企業や小さな会社における「リスクヘッジの考え方」について、3つのポイントをご紹介いたします。
中小企業のリスクヘッジの考え方
- 完全にリスクを回避することは、極めて困難であると心得る
- リスクを最小限に抑えようとする場合は、コストを計算する
- まずはリスクを取ることで得られる「リターン」を勘案する
リスクを避けることや、リスクを最小限に抑えることだけに注力すると、一時的にその場はしのげるかもしれませんが、いずれまた似たようなリスクが目の前に現れます。
積極的にリスクを取る必要はありませんが、リスクの程度をしっかり見極めて、そこから得られるリターンを多角的に分析し、会社と社員が成長する機会になると判断するなら、あえてリスクを取る選択は正しいと言えるでしょう。
リスクヘッジに対する考え方は、経営者の考え方や価値観によって大きく左右されるものですから、簡単に変えることは難しいかもしれませんが、
「なるほど、こういう考え方もあるのか…」
という視点でお読みいただき、参考にできる部分があれば取り入れていただければ幸いです。
それではひとつずつ詳しく見ていきましょう。
リスクを回避することは困難と心得る
中小企業のリスクヘッジの考え方、ひとつ目のポイントは「リスクを回避することは困難と心得る」です。
預言者や占い師であっても、未来の出来事を正確に言い当てることはできません。
「一寸先は闇」とはよく言ったもので、私たちは予測不可能な世の中を生きています。
会社が利益を求めて何かしらの活動を続ける限り、様々な問題が次から次に起こるのは当然であり、リスクを避けようと思っても避けられるものではありません。
「リスクを避ける」という表現を噛み砕くと、
「起こりうるリスクを想定し、それが起こるであろう方向には進まない」
という表現になるでしょうか。
確かに起こりうるリスクをある程度は予測することはできるかもしれませんが、先に申し上げたように未来を予測することは誰にもできません。
リスクを避けようと進んだ先に想定外の問題が発生したり、とにかく現状維持を貫いてじっとしていたとしても、動かないことによる問題(リスク)が発生します。
そう考えると、経営戦略やビジネス戦略においては、リスクを避けようと考えを巡らすこと自体が時間の浪費であり、ナンセンスと言えるでしょう。
リスクを抑えるためのコストは最小限に
中小企業のリスクヘッジの考え方、2つ目のポイントは「リスクを抑えるためのコストを計算する」です。
「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、予想されるリスクに備えておくことは決して悪いことではありませんが、その場合はリスクを抑えるために費やす時間と労力、コストなどを考えた上で、取り組む必要があります。
医療保険を例にとってご説明しましょう。
一般的な医療保険は手術や入院すると保険料が支払われます。このタイプの保険に加入した場合、仮に月額の保険料を3000円とすれば、年間で36000円の保険料を支払う計算になります。
貯蓄型の保険は別として、掛け捨ての保険は基本的に支払った保険料が返ってくる事はありませんから、手術や入院することがなければ、保険料として支払った36000円は1年間無事に過ごせた「安心料」として消えていくことになります。
問題はこの「安心料」が(自分にとって)高いのか?安いのか?ということです。
日本人の死因の上位を占めるがん(悪性新生物)をはじめ、急性心筋梗塞や脳卒中などの三大疾病に関しては、手術や入院費用も高額になるため、専用の保険に加入しておくと安心ですが、それ以外の病気で手術や入院を伴うケースはそれほど多くありません。
そう考えると、収入が多くお金に余裕のある方は別として、手術や入院する可能性が低いにもかかわらず、万が一のリスクを抑えるために毎月3000円のコストを費やす行為が、果たしていいのか悪いのか…少々疑問に感じるところです。
会社員であれば社会保険に加入していますし、自営業の方も基本的には国民健康保険に加入していますから、病気や怪我をしても治療費を全額自己負担する必要はありません。
大怪我をして手術することや入院することがあったとしても、1年のうちに何度も手術や入院を繰り返す可能性は極めて低いと言えるでしょう。
上記のことから、個人的には医療保険に入るつもりで毎月3000円を貯金や投資に回して、心配であれば三代疾病の医療保険のみ加入するという形でいいのではないか?と思ってしまいます。
普段から健康的な生活習慣を心がけていれば、手術や入院のリスクは下がりますし、仮に数年経ってから手術や入院することがあっても、毎年36000円ずつ医療保険の代わりに貯蓄していたお金を手術費や入院費に充てれば、場合によってはお釣りが帰ってくるかもしれません。
いろんな考え方があるので一概には言えませんが、毎月数千円の(掛け捨て型の)保険料を支払い続けるのは、長い目で見るとリスクに見合わない…そう思うのは私だけでしょうか。
リスクを最小限に抑える努力はすべきですが、リスクを抑えるためのコストを見極めて、
「起こりうるリスクに見合うものかどうか?」
はしっかり検討しておく必要があるでしょう。
上記のことから、ビジネス活動を行う上で、リスクを最小限に抑える場合は、できるだけコストをかけず「ほどほど」に備えることをオススメいたします。
リスクを取ることによるリターンを勘案
中小企業のリスクヘッジの考え方、3つ目のポイントは「リスクを取ることで得られるリターンを勘案する」です。
自社の現状をできるだけ正確に把握した上で、許容できるリスクの範囲を明確に定め、リスクを取ることで得られるリターンと比較、勘案します。
そして、得られるものが大きいと判断した場合は、あえてリスクがある方を選ぶ。
この手法の良いところは、リスクを避けようとしたり、リスクを抑えようとすることに一切の時間と労力を使うことなく、それらの時間と労力を全て「リターンを獲得する活動」に使えるところです。
新商品の開発や新たな人材の採用を例に解説しましょう。
商品開発は常に失敗するリスクと隣り合わせですし、人材採用も同様に、採用された人が実際に会社で働いてみるまで、どんな人かはわかりません。
いずれも多くの時間と労力が必要であり、少なからずコストを費やすことになる反面、その結果が保証されているわけではありませんから、リスクを伴う行為と言えます。
商品開発にチャレンジすることなく既存の商品を売り続けると、上記のリスクは回避できます。
人材採用に関していうと、人手が足りない場合、社員ではなく期間限定のアルバイトやパート、契約社員や派遣社員を雇うことで、会社とのミスマッチが生じても人件費を抑えたり、あらかじめ決められた期間で契約を終了することができますから、リスクを回避、あるいはリスクを抑えることが可能です。
では商品開発や人材採用におけるリターンはどのようなものがあるか?
パラダイムシフトといえば言い過ぎかもしれませんが、まずは見方を変えることから始めなくてはなりません。
「パラダイムシフト」とは、当然のことと考えられていた認識や思想、考え方や価値観などが劇的に変化することを言います。
つまり商品開発においては売り上げや利益が、人材採用においては採用された人の能力やスキル、会社への適応力や貢献度が重要であると考えられていますが、その他にも商品開発や人材採用を行うメリットはないか?という見方をしてみるのです。
考えた末、商品開発はそれを担当する社員にとって、絶好の成長機会だと気が付いたとしましょう。
商品を開発する過程において創造力や主体性が養われますし、デザインやマーケティングに関する知識や考え方も身に付く他、他部署との連携やメンバー間の意見調整を行う中でコミュニケーション能力も磨かれます。
採用活動に関しても、正社員を採用するとなると「会社が求める人物像」「この会社で活躍できる人材」についてあらためて考える機会になりますし、採用した後の新人研修を見直すきっかけにもなります。
パラダイムシフトを行って「見方を変える」ことで、上記のような隠れたメリット、つまり「リターン」に気づくことができれば、リスクを承知の上で「チームを作って商品開発する」ことも、「正社員の採用活動を開始する」ことも、悪い選択肢ではなくなります。
多少のリスクを伴うでしょうが、それ以上に貴重な経験が社員の成長を加速させたり、新たな取り組みがノウハウとなり、会社の財産となることを考慮すると、リスクを選ぶことで得られるリターンの方が大きいという見方もできます。
たとえ商品開発が失敗に終わっても、その経験から得た知識やスキル、悔しさや自分に足りないものに気づけたことが次の仕事で活かされ、大きな成果を生み出すかもしれません。
思っていたような人材を採用できなかったとしても、それを機に採用活動の大幅な改善が為されたり、会社にとってどのような人材を最も評価すべきか?といった人事の方針が抜本的に見直され、人事評価制度や評価基準の刷新につながることもあるでしょう。
まとめ
今回は
- 中小企業の生き残り戦略
- 中小企業における商品開発の意味
- 中小企業のリスクヘッジの考え方
について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、もう一度「中小企業の生き残り戦略」と「中小企業のリスクヘッジの考え方」をおさらいしておきましょう。
中小企業の生き残り戦略
- 自社商品を開発することで、独自のノウハウを蓄積できる
- 自社商品の開発を経験することで、本物の人材を育成できる
- 自社商品を開発すること自体が、会社の危機管理に直結する
中小企業のリスクヘッジの考え方
- 完全にリスクを回避することは、極めて困難であると心得る
- リスクを最小限に抑えようとする場合は、コストを計算する
- まずはリスクを取ることで得られる「リターン」を勘案する
自社でオリジナル商品を開発するとなると、何もかもがゼロからのスタートのように感じるかもしれませんが、逆にいうと、その分だけ吸収できるものが多く、学びの機会が与えられるということ。
初めて商品開発にチャレンジする企業様は、既存の商品やサービスに近いものから新たな商品を開発するのがオススメです。
私がネット印刷で勤めていた頃、新サービスとして「名入れボールペン」をスタートさせました。
自社の設備では(当時は)紙への印刷しかできなかったので、名入れペンは未知の領域でしたが、「印刷する」という意味では共通していたので、サービスを開始するにあたって、それほど抵抗を感じなかったことを覚えています。
余談になりますが、名入れボールペンの事業は、私が会社を去る頃には年間数千万円の売上をつくるまでに成長して、それなりの結果を残すことができました。
さらにもうひとつ、「既存商品のリニューアル」について、少しだけお話ししたいと思います。
既存商品のリニューアルは、「商品自体に大きな変更を加える必要はない」というのが私の考えです。
では、どのような姿勢で商品のリニューアルを行うのか?
今一度いろんな角度から商品を見直して、社会の変化や流行などを嗅ぎ分けながら新たな客層へのアプローチを試みます。
つまり、既に販売している商品の新たな切り口を見つけ、今の時代に適した売り方や販促プロモーションを行い、これまでとは違うメリットを打ち出すことで、顧客ターゲットや販路を拡大するという方法です。
例えば、私が愛飲している「ヤクルト」の場合、新しい商品が次から次に発売されるわけではありませんが、ヤクルトに含まれている成分が健康をサポートするさまざまな働きがあることを新たに実証し、その情報をWebサイトやチラシで発信しています。
我が家にも「お届けに来ました~」という手書きのメモと一緒に、そのようなチラシが何度かポストに入っていました。
一般的なポスティングチラシは一目見て必要ないと判断したら即ゴミ箱行きですが、ヤクルトさんのチラシはひとまず家の中に持ち帰りますから、自然と家族も手に取ります。
そこでチラシの内容を見て「だったら私もヤクルト飲もうかな」となるわけです。
ご存知の通り、ロングセラー商品であるヤクルトは、ヤクルトレディさんをはじめとする独自の販促活動を展開しながらも、「病気を未然に防ごう(未病)」という健康志向を背景に、これまでにない新たな切り口を見つけて「既存の販売活動」と掛け合わせることで、新たな顧客を取り込んでおられます。
本当に素晴らしいですね。(ヤクルトさんいつもありがとう、そしてこれからも飲み続けます!)
アサヒビールのスーパードライが大ヒットして業界の地図を塗り替えたように、アップル社がiMacを開発してその名を一気に広めたように、新商品や新サービスが爆発的にヒットすれば、会社の未来を変えるほど大きなインパクトを与えます。
一方で「ロングセラー」「定番」と呼ばれる既存の商品は、季節に応じて味や素材をアレンジしたり、年中行事をきっかけにキャンペーンを行うなど、手を変え品を変え「飽きさせない」「忘れさせない」ような販促活動を行うことで息を吹き返すことが往々にしてあります。
ヒット商品を生み出す商品開発と、既存商品の売上アップ。
この2つの活動をバランス良く取り入れることが、景気に左右されにくい、継続的な業績アップにつながるのではないでしょうか。
最後にもうひとつ。
「日々の業務に追われて、重要な仕事に費やす時間が足りない…」
「経営戦略や人事、新事業について専門分野の人に相談したい…」
という経営者・役員・マネージャーの皆様に画期的なサービスを2つご紹介いたします。
そのサービスとは、
- オンラインアシスタント
- スポットコンサルティング
です。
オンラインアシスタントとは、経理や総務、人事や労務、財務や法務、営業やマーケティングといった様々な分野の専門的な知識やスキル、実務経験を持った外部(社外)の人材が、オンライン上で自社の業務をサポートしてくれる便利なサービスです。
慢性的な人材不足が続き、リモートワークが珍しいものではなくなった今日、月額数万円から依頼できるオンラインアシスタントが、契約社員やパート社員に取って代わる選択肢のひとつとして、あるいは、多忙な経営者やマネージャーの秘書として活躍してくれます。
スポットコンサルティングとは、ピンポイントで知りたい情報やアドバイスしてほしいことを、特定の業界や業務において豊富な経験を持った「その道のプロ」やコンサルタントに、1時間単位で気軽に相談できる便利なサービスです。
こちらのサービスも、意思決定に欠かせない貴重な判断材料(情報)が安価で手に入ることから、経営者のみならず、管理職や事業責任者、商品の開発責任者など、様々なポジションの方に利用されています。
いずれのサービスも、スピード感を持って会社経営を行う上では利用価値が高いサービスなので、少しでも気になる方は是非チェックしてみてくださいね。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)