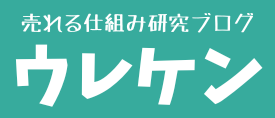「職場の人間関係のを改善するコツは?」
「職場の人間関係がうまくいかない時、管理職は何をすべきか?」
「職場の人間関係がうまくいく方法を知りたい」
というあなたに、今回は、
- 職場の人間関係を改善するための「7つのコツ」
- 職場の人間関係改善に向けて「管理職が果たすべき役割」
- 職場の人間関係の改善するための「たったひとつの方法」
について、わかりやすく解説いたします。
職場の人間関係に頭を悩ませている人が多い中、当事者ではないけれども、管理職という立場にあって、対策や乗り越え方を模索している方も多いのではないでしょうか。
私も卸売業者にいた頃は主任として、ネット印刷では営業部長やマーケティング部のサブマネージャーとして、多くの部下を率いて仕事をしていましたから、少なからず、職場の人間関係による事件やトラブルは何度か遭遇しました。
というか、今あらためて当時のことを振り返ると、大小はあれど、常に何かしらの人間関係に関する問題を抱えながらマネジメントしていたように思います。
上手に解消できた問題もあれば、当事者が退職するという形で幕引きになった事件もあり、未だに
「あの時、どうすれば良かったのか…」
と、ふと考えることもあります。
部署を任されている管理職ともなれば、職場の人間関係が悪化している現状を放ってはおけませんから、何かしらの解決策や対処法を考えて実践するわけですが、実際のところ、表面的には解決できたとしても、当事者の心のわだかまりをスッキリ解消するには、本人の自助努力も必要です。
答えとは、誰かに教えてもらうものではなく、自らの手で導き出していくべきものです。
他者から与えられた答えはしょせん対処療法にすぎず、何の価値もありません。
出典:岸見一郎 古賀史健(2013)『嫌われる勇気ー自己啓発の源流「アドラー」の教え』ダイヤモンド社.
とはいうものの、職場の人間関係を改善しなければ生産性や業務効率も上がりませんから、何らかの対策を打つ必要があります。
これからご紹介する内容は、あくまで「職場の人間関係を改善するコツ」であり、「管理職が果たすべき役割」であって、「職場の人間関係を完全に取り除く方法」ではありません。
しかし、たとえ職場の人間関係を根こそぎ取り除くことができなかったとしても、管理職としての役割を全うし、経験を重ねるうちに、だんだんと人間への理解が深まり、管理職にとって欠かすことのできない洞察力も鍛えられ、問題が大きくなる前に対処できるようになります。
それでは早速見ていきましょう。
職場の人間関係を改善するコツ
職場の人間関係を改善するコツを7つご紹介いたします。
職場の人間関係を改善するコツ
- 自分から積極的に挨拶を行う
- 些細なことも職場内で共有する
- 感謝の気持ちを直接伝える
- 相手の立場になって考える
- 相手の話を遮らず最後まで聞く
- 相手を無理に変えようとしない
- 相手との共通点を見つける
まず大前提として、職場の人間関係を改善するには、それ相応の時間が必要です。
職場の人間関係ががギスギス、あるいはギクシャクしている場合は最低でも数ヶ月、職場の人間関係が最悪な場合は改善するまで1年以上かかることも珍しくありません。
なので、本気で職場の人間関係を改善したいのであれば、改善に向けた行動を、あきらめずにコツコツと継続することが何よりも大切です。
とはいうものの、世の中には自分の想像を絶する価値観や考え方を持った方もいるので、場合によっては少ししか改善されないかもしれませんが、先にご紹介した「職場の人間関係を改善するコツ」を実践し続けることで確実に改善されます。
それでは早速「職場の人間関係を改善する7つのコツ」をひとつずつ見ていきましょう。
自分から積極的に挨拶を行う
職場の人間関係を改善する7つのコツ、ひとつ目は「自分から積極的に挨拶を行う」です。
挨拶には様々なプラスの効果があります。例えば…
- 相手の存在を認め、相手の自己重要感を満たすことができる
- マナーが良い人と思ってもらえる他、相手に好印象を与える
- コミュニケーションの敷居が下がり、会話が生まれやすくなる
- 返報性の法則によって、相手も挨拶をしてくれるようになる
- 挨拶をすると自分も相手も気持ちが良くなり、気分が晴れる
など、挨拶をしてマイナスに作用することは何ひとつありません。
ただし、上記の効果を実感するには、特定の人物だけでなく出会う人全てに挨拶をするとともに、毎日欠かさず継続的に挨拶を続ける必要があります。
挨拶をして嫌な気持ちになる人はいませんし、挨拶をされて気分を悪くする人もいません。
なので、職場の人間関係を改善したい方はもちろん、少しでもギクシャクしていると感じた時は、まずは挨拶を徹底することから始めてみましょう。
些細なことも職場内で共有する
職場の人間関係を改善する7つのコツ、2つ目は「些細なことも職場内で共有する」です。
情報共有には多くのメリットがあり、職場の人間関係の改善にも一定の効果があります。
例えば、
- 業務の「見える化」によって業務効率や生産性が向上し、職場内に活気が生まれる
- 仕事の属人化を防止できるので、誰かが休んだり退職しても業務に支障が出にくい
- 「聞いていない」「知らなかった」から生じる怒りや不満を減らすことができる
など、情報共有によって業務が円滑に行われると、結果として職場の人間関係が悪くなる要因が少なくなるので、職場の人間関係が好転することはあっても、悪くなることはありません。
感謝の気持ちを直接伝える
職場の人間関係を改善する7つのコツ、3つ目は「感謝の気持ちを直接伝える」です。
「いつもありがとう」
「いや〜ホントに助かったよ、ありがとう」
「先日はありがとうございました」
感謝の言葉を伝えると、伝えた側と受け取った側、双方にプラスの効果が生まれることをご存知でしょうか。
感謝の言葉を発すると幸せホルモン「オキシトシン」の分泌が活発となるため、ストレスの緩和や免疫力アップが期待できる他、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
加えて、感謝の言葉を伝えるには相手の良いところを見つけなければなりませんから、感謝の言葉を伝えれば伝えるほど相手の長所を発見することができるので、今まで以上に好意的な気持ちで相手に接することができるというわけです。
感謝の言葉を受け取った人は、自分の仕事を認めてもらえたことで自信が生まれ、モチベーションが上がり、今まで以上に意欲的にお仕事に取り組めるようになります。
さらに、感謝の言葉を伝えてくれた人に対して好意的な気持ちや仲間意識が芽生え、相手に対しても感謝の気持ちを抱くようになり、職場の人間関係を改善する際に必ず必要となる「信頼関係」を築く土台が出来上がります。
誰かに言葉をかけるとき、それは「愛語(あいご)」でなければなりません。
愛語とは、仏教の世界の言葉ですが、端的に言えば、「聞いた人が喜びを感じる、相手が聞きたいと思う言葉」のことです。
出典:アルボムッレ・スマナサーラ(2012)『一生、仕事で悩まないためのブッダの教え』株式会社三笠書房.
相手の立場になって考える
職場の人間関係を改善する7つのコツ、4つ目は「相手の立場になって考える」です。
自分のことしか考えていないスタッフが増えれば増えるほど、職場の人間関係はギクシャクします。
相手の立場になって考えられる人が増えれば増えるほど、職場の人間関係はますます円滑になり、助け合いや感謝の輪が広がります。
「相手の立場になって考える」とは、「相手にとってプラスになるように考える」のではなく、「相手にとっても自分にとってもプラスになるように考える」ことに他なりません。
では、相手の立場になって考える人を増やすにはどうすればいいか?
それは、まずあなたが「相手の立場になって考える」こと、そして、それを継続することです。
それ以外に方法はありません。
相手の話を遮らず最後まで聞く
職場の人間関係を改善する7つのコツ、5つ目は「相手の話を遮らず最後まで聞く」です。
人が最も興味を抱いている対象は何か?
答えは「自分」です。
そんな「自分」の話を遮ることなく、相槌を打ちながら最後まで熱心に聞いてくれる人が目の前にいたら、あなたはどんな印象を受けますか?
良い印象を抱くことはあっても、悪い印象を抱く人は誰一人いないでしょう。
会議やミーティングをはじめ、個別の面談など、職場内ではスタッフ同士で話す機会が多々ありますが、相手の話を遮らず最後まで聞くことを徹底すると、「この人は自分の話をちゃんと聞いてくれる」と思ってくれるので、やがては本音で話ができるようになります。
そして、腹を割って話ができるようになれば、信頼関係を築ける日も遠くないでしょう。
相手を無理に変えようとしない
職場の人間関係を改善する7つのコツ、6つ目は「相手を無理に変えようとしない」です。
人は誰しも自分の考えが「正しい」と思いがちで、異なる意見や考えを持っている相手は「間違っている」という捉え方をする傾向があります。
そして、自分と異なる意見や考えを耳にした時、自分に自信がある人ほど、厄介なことに自分の考えが正しいことを相手に認めさせようとします。
一方で、相手の意見や考えをあるがまま受け止められる人は、自分と異なる意見や考えを耳にしても
「おもしろい意見だなぁ」
「そういう考え方もあるのか」
「彼(彼女)らしい意見だね」
といったん受け止めて、相手の意見や考えを無理に変えようとせずに、相手の意図や真意を見極めながら慎重に話を進めます。
相手の意見や考えに沿わない決定を下す際も、こちらの考えに「従わせる」「押し切る」のではなく、彼や彼女に理解を求めながら丁寧に説明して、できる限り遺恨が残らなように努めましょう。
相手との共通点を見つける
職場の人間関係を改善する7つのコツ、7つ目は「相手との共通点を見つける」です。
相手との共通点を見つけると、「この人は自分と同じ価値観を持っている」「この人は自分と気が合うかもしれない」と感じて、親近感や仲間意識が生まれます。
とりわけ、お互いに自分の趣味趣向に共通点が見つかった場合、相手のことを一気に好感が持てるようになることも珍しくありません。
では、相手との共通点を見つけるにはどうすればいいか?
日頃から自分の趣味や好きなもの、好きな本や好きな映画、好きな場所や今ハマっていることなどを、相手が嫌がらない程度にサラッと話すことです。
相手と共通点が見つかれば、自然と話が盛り上がってくるので、その時に熱弁すれば相手もそれに呼応するかのように、熱っぽく話してくれるでしょう。
そして、次に会った時はおたがいに笑顔で挨拶を交わせるはずです。
職場の人間関係の改善における管理職の役割
職場の人間関係を改善するために、管理職が果たすべき役割とは何か?
管理職の仕事は、主に部下をマネジメントすることによって、会社から任された組織(部署)の成果をあげることに他なりません。
具体的な仕事は、
情報の共有:会社のビジョンやミッションをはじめ、自分たち(組織)に課せられた目的や目標を浸透させる。
業務の遂行:業務が円滑に遂行できるように進捗を管理し、課題を解決へと導き、職場環境の改善に取り組む。
チーム作り:部下の個性や能力を見極めることで、それぞれの長所を活かし、短所を補い合える体制を整える。
法令の遵守:労働に関する法律を守って、個人情報や機密情報を適切に管理し、職場のハラスメントを取り除く。
などがあり、職場の人間関係の改善は「チーム作り」や「法令の遵守」に関わる大切な仕事です。
しかし、現実は
「職場の人間関係の改善まで、なぜ管理職がやらなければならないの?」
と思っている人が少なくありません。
それもそのはず、管理職を任される人は、仕事に対する成果や手腕が認められたことで管理職になった人が大半で、とりわけ、管理職になったばかりの人は、職場の人間関係を改善することに関しては慣れておらず、どう対処していいか頭を悩ませている人が、驚くほど多いのです。
そんなみなさまのお役に立てるように、ここでは、職場の人間関係の状況を3段階に分けて、それぞれの状況における管理職の役割をご紹介いたします。
今現在、職場の人間関係がギクシャクしている、またはギスギスしている、あるいはすでにバラバラで崩壊しつつある…という方は、ぜひ参考になさってください。
職場の人間関係を改善するために管理職がすべきこと
- 苦手意識や性格の不一致による職場の人間関係を改善するには、管理職からの「的確なアドバイス」が有効
- 少しでもストレスが発生している職場の人間関係を改善するには、管理職が「改善につながる具体策を示す」
- 感情的な衝突が起きている職場の人間関係を改善するには、管理職が「仲裁に入って問題の原因を取り除く」
それではひとつずつ詳しく見ていきましょう。
苦手意識による人間関係の問題
職場の人間関係を改善するために管理職がすべきこと、
最初は「苦手意識による人間関係の問題」への対応です。
人はそれぞれ違った考え方や価値観を持っていますから、良好な人間関係を築くためには、時には自分の考えをいったん脇に置いて、相手の考えや価値観を尊重する必要があります。
しかし、自分の考えや価値観への執着が強い人は、厄介なことに、自分とは真逆の考えや価値観を持つ人に対して、次第に苦手意識を持つように…。
苦手意識を持つだけならいいのですが、それがエスカレートすると表情や話し方にまで現れ、場合によっては嫌悪感を抱くようになり、露骨な態度を表すようにまで発展すると、人間関係に亀裂が生じて、業務に支障をきたす恐れがあります。
そんなことにならないように、例えば、
部下Aの発言や行動に対して、苦手意識を抱いている部下がいる場合は、
- 部下Aと面談の場を設け、自身の発言や言動の意図を確かめた上で、必要であれば改善を促す
- 部下Aに苦手意識を抱いている人に対し、接し方や付き合い方、心の持ち方などを的確にアドバイスする
など、適切な対応が求められます。
ストレスによる人間関係の問題
職場の人間関係を改善するために管理職がすべきこと、
次に「ストレスによる人間関係の問題」への対応です。
苦手意識だけにとどまらず、他のスタッフの発言や行動に対して少なからずストレスを感じている部下がいる場合は、具体的な改善策を考え、できるだけ早く実行に移す必要があります。
ストレスが大きくなると、仕事に集中できなくなるだけでなく、体の免疫力が低下するため、体調を崩しやすくなり、ひどくなると手足の痙攣や痺れ、頭痛やめまい、下痢や吐き気、動悸や息切れなど、身体的な症状にまで発展して、最悪の場合はうつになって長期療養、ひいては退職せざるを得ない状況に追い込まれます。
そんなことにならないように、例えば、
部下Aの発言や行動に対して、ストレスを感じている部下が1名以上いる場合は、
- ストレスを与えている部下に対し、まずは発言や行動の意図を確かめて、問題があれば改善を促す
- ストレスを受けている部下に対しては、ストレスの原因を明らかにして、改善につながる具体策を施す
など、早急な対応が必要です。
ストレスが小さいうちは、早めの対策や休暇を取るなどして、抑制・解消・発散することもできますが、ストレスが大きくなると確実に問題が長期化しますから、くどいようですが、見過ごすことなく早急な対応が求められます。
感情的な衝突による人間関係の問題
職場の人間関係を改善するために管理職がすべきこと、
最後は「感情的な衝突による人間関係の問題」への対応です。
私は正しい。
すなわち相手は間違っている。
そう思った時点で、議論の焦点は「主張の正しさ」から「対人関係のあり方」に移ってしまいます。
つまり、「私は正しい」という確信が「この人は間違っている」との思い込みにつながり、最終的に「だから私は勝たねばならない」と勝ち負けを争ってしまう。
出典:岸見一郎 古賀史健(2013)『嫌われる勇気ー自己啓発の源流「アドラー」の教え』ダイヤモンド社.
そもそも主張の正しさは、勝ち負けとは関係ありません。
あなたが正しいと思うのなら、他の人がどんな意見であれ、そこで完結するべき話です。
ところが、多くの人は権力争いに突入し、他者を屈服させようとする。
だからこそ、「自分の誤りを認めること」を、そのまま「負けを認めること」と考えてしまうわけです。
出典:岸見一郎 古賀史健(2013)『嫌われる勇気ー自己啓発の源流「アドラー」の教え』ダイヤモンド社.
上記が示す通り、感情的な争いは相手を屈服させるまで続きます。
そして、屈服させられた相手は「負かされたこと」をいつまでも覚えていて、必ず復讐します。
そうなると、もう手がつけられません。
そんなことにならないように、例えば、
部下Aの「感情的な発言や行動」「攻撃的な態度」が原因で衝突が起きている場合は、
- 感情的な衝突においては当事者同士の解決が難しいため、管理者が仲裁に入る
- 個別に呼び出して、それぞれの言い分を聞いた上で、状況を正確に把握する
- 当事者たちに対して、「問題の決着を管理者に委ねること」に同意してもらう
- 2度と同じことが起こらないように、問題の原因を根本的に取り除く決定を下す
- 決定に至った経緯や理由を当事者に伝えて、できるだけ速やかに実行する
など、第3者である管理職が明確な結論を出して、問題を決着させます。
管理職による決定を不服とし、場合によっては遺恨が残る場合もありますし、一方が「納得できない」という理由で会社を離れることになったとしても、こればかりは仕方ありません。


職場の人間関係を改善する唯一の方法とは?
職場の人間関係の改善方法は、果たして存在するのか?
いつの時代も、職場の人間関係によるトラブルや事件が後を絶たないことを考えると、
「特効薬は未だ見つかっていない」
というのが正直なところではないでしょうか。
むしろ、職場の人間関係による問題は、
「以前に比べて増えている」
と言っても過言ではありません。
あくまで個人的な見解ではありますが、私が大学を卒業して、新卒で入社したころは、〇〇ハラスメントという言葉も耳にしたことがありませんでしたし、ニュースを見ても、今ほど職場の人間関係による事件や事故も少なかったように思います。
では、なぜこれほど多くの問題を抱えている「職場の人間関係」の改善方法が、いつまでたっても見つからないのか?
それは、
「人間は本来、自分勝手でわがままな生き物」
であり、多くの人は、
「自分勝手でわがままな生き物であることを認めたくない」
からです。
まず第一に大切なことは「自分はわがままである」と正直に認めることです。
人は自分が自分勝手な人間だということを認めたくありません。
けれども私たちは仏教的な正しい立場に立ちましょう。
それは別に難しいことではなくて、「所詮生命というのは自己愛で、わがままで、自分の幸福、自分の利益を考えて生きている」ということを理解することなのです。
出典:アルボムッレ・スマナサーラ(2011)『アルボムッレ・スマナサーラ法話集 人付き合いの処方箋』株式会社アルマット.
もちろん、すべての人間が自分勝手でわがままに振る舞っているというわけではありません。
わかりやすい例を挙げると、「マザーテレサ」のように、貧困や病に苦しむ人々を救うために生涯を捧げた人物もいますし、子供を持つ親は少なからず自分の子供のことをいちばんに考えているのではないでしょうか。
しかし、職場の人間関係ともなると、ついつい自分のことを優先しがちです。
なぜなら、職場では「共存」よりも、「競争」が勝ってしまうから。
対人関係の軸に「競争」があると、人は対人関係の悩みから逃れられず、不幸から逃れることができません。
出典:岸見一郎 古賀史健(2013)『嫌われる勇気ー自己啓発の源流「アドラー」の教え』ダイヤモンド社.
では、職場の人間関係の改善方法はないのでしょうか?
そんなことはありません。
職場の人間関係の改善方法はあります。
簡単ではありませんが、とってもシンプルな方法があります。
『自分、自分』と自分ばかりに向かっている内向きのエネルギーをほんの少々、人のために外に向けて使いましょうということです。
ほんの少しでも強引に、エネルギーを他人のために使うと、人づきあいというのはとてもスムースにいきます。
心のエネルギーを外向きに使えば使うほど、人づきあいはうまくいくようになります。
出典:アルボムッレ・スマナサーラ(2011)『アルボムッレ・スマナサーラ法話集 人付き合いの処方箋』株式会社アルマット.
いかがですか?
言葉にすれば簡単ですが、上記の方法を行動に移すためには、先に申し上げたように、
「自分がわがままであることを認めた上で、相手のためにエネルギーを使う」
必要があります。
上記のことから、職場の人間関係を根本的に改善する方法があるとすれば、まずは社長や幹部、管理職をはじめとする役職者が自ら実践し、全ての従業員に伝播するまで根気よく続ける。
それでも職場の人間関係が完全に良くならないかもしれませんが、今よりも改善することだけは間違いありません。


まとめ
今回は、職場の人間関係を改善するためのコツや、職場の人間関係改善に向けて管理職が果たすべき役割、職場の人間関係の改善するためのたったひとつの方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
「管理職にだけはなりたくない」
「会社で出世することに興味がない」
そんな若者が増えているような話を時おり耳にします。
確かに、管理職になると給与は増えるかもしれませんが、それに伴って責任がのしかかり、仕事の範囲が一気に広がって、今まで取り組んできた仕事以外の仕事、つまり「マネジメント」という大きな仕事が追加されます。
そう考えると、
「割りに合わない」
と考えるのも無理はありませんし、納得できます。
おまけに、学校の教員とは異なり、管理職は「教育実習」もありませんから、基本的には「ぶっつけ本番」です。
それを見越した上で、管理職に向けた研修を積極的に行っている企業もありますが、その大半は大企業であって、多くの中小企業や小さい会社、とりわけ慢性的に人材が不足している会社や、退職率が高い会社は、入社して2、3年の社員がいきなり管理職を任されることも珍しくありません。
かくいう私もそうでした。
役職を持たない従業員をケアすることも大切ですが、上記のことを勘案すると、
「管理職こそ会社からの手厚いサポートが必要不可欠」
と考えるのは私だけでしょうか。
心のサポートはもちろん、具体策として、会社は
- 管理職を選ぶときの選考基準を設ける
- 管理職の役割を箇条書きで明確に示す
- 管理職の裁量権を明文化し、公開する
など、管理職の仕事や役割を社内に浸透させることに注力すべきでしょう。
そうすることによって、管理職は今まで以上に働きやすくなりますし、職場の人間関係が悪化したときも迅速に対応できます。
管理職もひとりの人間です。
会社の将来を真剣に考えている、部下のことを親身になって考えている…そんな管理職ほど、責任感が強い反面、精神的な負担も大きく、心労が絶えません。
「管理職も悪くない」
「管理職になってみたい」
そう思える社員が一人でも増えるように、会社は今まで以上に管理職のあり方を見直すべきではないでしょうか。
みなさんはどう思われますか?(特に現役管理職の方)
最後に、大切なことをもうひとつ。
もしあなたが職場の人間関係によるストレスで、心が疲れている…誰かに悩みを聞いて欲しい…解決策について相談したい…気持ちを落ち着かせたい…という場合は「オンラインカウンセリング」の利用をおすすめいたします。
オンラインカウンセリングとは、臨床心理士や国家資格を持つカウンセラーと1対1で約50分程度、オンライン上で気軽に悩みを相談できるサービスです。
具体的には、
- 自分の感情を素直に表現し、悩みを打ち明けることによって気持ちを落ち着かせる
- 日頃から抱えている悩みや問題をカウンセラーと一緒に考えて、解決の糸口を見出す
- 心の中にしまっていた気持ちを話すことで、今置かれているの自分の状況を整理する
- カウンセラー(専門家)の話を聞くことで、客観的な視点から自分の考えを認識する
ことによって、
ひとりで抱え込んでいた不安や悩みを和らげ、心の健康を取り戻す効果が期待できます。
私がそうであったように、心の不調が身体的な症状(心身症)に発展すると、心と体が健康な状態に戻るまで数ヶ月~数年かかることも珍しくありません。
なので、今現在、職場の人間関係による強いストレスや大きな不安を抱えていらっしゃる方は、自分の心と体を最優先に考えて、オンラインカウンセリングに限らず、心のケアやリフレッシュ、あるいは、ストレスの原因から距離を置くことを検討してみましょう。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました (^.^)