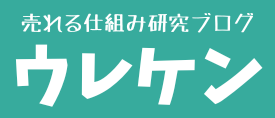「企画を考えるときのコツが知りたい」
「企画を考える力を身につけたい」
「企画を出す上で、自分なりのスタイルを確立したい」
とうあなたに、今回は
- 企画を考えるときのコツ
- 企画力を鍛える方法
について解説いたします。
企画は学校のテストのように明確な答えが無く、企画を実行に移して結果を見届けるまでは、それが正解かどうかは誰にもわかりません。
数多くの企画を世に送り出し、その結果を検証してきた人間であれば、出来上がった企画の内容を見ただけで、おおよその結果を予測できるかもしれませんが、そうでない場合は「やってみるまでわからない」というのが正直なところです。
ただし、企画を考える上で、
- これだけは押さえておかなければならない
- これを無視すると大抵はうまくいかない
という「ポイント」は存在します。
そして、これからお伝えする内容は、いずれもその「ポイント」が鍵を握っています。
それでは早速見ていきましょう。
企画を考えるコツ
いい企画を考えるコツはあるのか?
あるとすれば、どのようなものか?
いい企画とは最初にある程度、意表をつくものであり、かつそれが出てくると、「なぜ、今までこれがなかったのだろう」と思わせるものです。
出典:斎藤孝(2011)『斎藤孝の企画塾 これでアイデアがドンドン浮かぶ!』株式会社筑摩書房.
上記の通り、「いい企画」とは、それを見たときに多くの人が反応を示します。
「反応を示す」とは、つまり、企画を実行に移すことによって「人の心を動かす」ということ。
そして、いい企画を考えるコツがあるとすれば、それは、企画を考える前に、「人の心が動くときは、どのようなときか?」を明らかにすることです。
企画というものは、人工的に「波」を作り出すことによって人の心を動かし、ターゲットとする人が自らの意思で「行動」を起こすように促すことに他なりません。
とりわけ、ビジネス活動における企画の目的は、消費者の注目を集める「波」を起こし、心を動かすことによって、商品の購入やお店への来店、サービスのお申し込みや会員登録という名の「行動」を起こさせること。
つまり、企画とは、最初に「人の心を動かす」ことができなければ、大きな成果は期待できません。
そのため、
「どうすれば人の心を動かす企画を生み出すことができるのか?」
と考えるのではなく、まずはじめに、
「人の心が動くときは、どのようなときか?」
を明らかにした上で、ターゲットとする人々の心を大きく揺さぶる「ビッグウェーブ」を起こす必要があります。
では、上記の「企画を考えるコツ」をつかむためには、あるいは、自分のものにするためにはどうすればいいのか?
それは、「企画力を鍛える」意外に方法はありません。
企画力を鍛える方法
企画力を鍛える方法を、4つのステップに分けて解説いたします。
「企画力=企画を生み出す力」と仮定するならば、これからご紹介する「企画力を鍛える方法」は、自らの力で自在に企画を生み出せるようになるための訓練といったところでしょうか。
あるいは、前項でお伝えした「企画を考えるコツ」を自分のものにするための訓練と言い換えることもできます。
企画力を鍛える方法 4つのステップ
- 「人の心が動くときは、どのようなときか?」を、思いつく限りリストアップする
- 適切な質問を投げかけることによって、自分が心を動かされた出来事を思い出す
- 自分が心を動かされた出来事を掘り下げて、「心を動かされたポイント」を探る
- 「心を動かされたポイント」をもとに、自分なりの仮説を立て、それを抽象化する
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
心が動くのはどんなとき?
企画力を鍛える方法、最初のステップは
「人の心が動くときは、どのようなときか?」を思いつく限りリストアップします。
ただ漠然と
「どうすれば人の心を動かすことができるのか?」
と考えたところで、そう簡単に答えは見つかりませんから、
「人の心が動く瞬間や出来事、きっかけや場面はどういったものがあるか?」
を、まずはじめに考えます。
自分の過去の経験をもとに考えてもかまいませんし、周りの人に聞いてもいいですし、人がたくさん集まる場所や、多くの人が使っているもの、人気の映画やテレビ番組から、仮説を立てるのもアリです。
一例を挙げると、
- 心がホッと温まる「なつかしさ」を感じたとき
- 目を奪われるほどの「美しさ」に出会ったとき
- 時間を忘れるほどの「おもしろさ」を体験したとき
などがあります。
もちろん、他にもたくさんの「人の心が動くとき」がありますので、宝探しのような感覚で、探してみてください。
適切な質問を投げかける
企画力を鍛える方法、次のステップは
適切な質問を投げかけることによって、自分が心を動かされた出来事を思い出してみます。
ここでは、最初のステップで導き出した「人の心が動くとき」を質問のカタチにして、自分に問いかけてみましょう。
例えば、こんな感じ。
「心がホッと温まる懐かしさ」を質問形式にすると…
→最近「懐かしいなぁ」と感じたことはある?そのきっかけは?
「目を奪われるほどの美しさ」を質問形式にすると…
→色や形、デザインなど、外見に目を奪われて購入した商品は何?
「時間を忘れるほどの面白さ」を質問形式にすると…
→時間を忘れるくらい没頭できるものは何?今ハマっているものは?
いかがでしょう。
質問形式にすると、答えにたどり着きやすくなるような気がしませんか?
ただし、質問が完成したからといって、早急に答えを出そうと焦ってはいけません。
質問が完成すれば、その答えをじっくりと考え続けます。
忘れっぽい人は、デスクの前に付箋を貼ってもいいですし、質問を書いたメモを持ち歩いてもかまいません。
すぐに答えが出なくても、無意識のうちに脳が勝手に考えてくれますから、焦らず急がず、答えが降りてくるのをじっくりと待ちましょう。
心を動かされたポイントは?
企画力を鍛える方法、3つ目のステップは
自分が心を動かされた出来事を掘り下げて、「心を動かされたポイント」を探ります。
ここでは、「自分が何に心を動かされたのか?」を具体的に掘り下げていきます。
例えば、
「色や形、デザインなど、外見に目を奪われて購入した商品は何?」
という質問に対する答えが「自転車」だったなら、
- 自転車のどの部分が特に気に入ったのか?
- 最終的に、自転車を購入する決め手になった部分はどこか?
を詳細まで明らかにするのです。
そうすることで、「心を動かされたポイント」が浮き彫りになってきます。
ちなみに、
「もとから自転車を買うつもりでお店に行って、ズラリと並んでいる自転車の中から自分の好きな色である赤を選んだから、赤い色が決め手になった」
というケース…これはまったく参考になりません。
参考になるのは、
「自転車を買うつもりはなかったけど、〇〇に心を奪われたので思わず購入してしまった」
というケースです。
このとき、
「〇〇が気に入ったので」の、「〇〇」にあたる部分が、まさに企画のヒントになります。
仮説を立てて、抽象化する
企画力を鍛える方法、最後のステップは
「心を動かされたポイント」をもとに、自分なりの仮説を立てて、それを抽象化します。
前のステップでは、「自分が何に心を動かされたのか?」を具体的に掘り下げましたが、「心を動かされたポイント」はそのままの状態では、企画のヒントにすることはできません。
では、どうすれば企画のヒントとして使うことができるのか?
「心を動かされたポイント」を抽象化して、企画のヒントとして使えるように加工します。
例えば、あなたが
「見た目がハーレーダビッドソン(アメリカのオートバイメーカー)のような自転車」
に心を奪われたとしましょう。
このままの状態だと、
「心を動かされたポイント=ハーレーダビッドソンのようなデザイン」
となりますが、
「ハーレーダビッドソンのような〇〇」
という企画を出せば、心を動かすことができるのか?というと、そんなことはないですよね。
そこで、心を奪われたポイントを「抽象化」するために、自分なりの仮説を立てます。
コアなファンを持つハーレーダビッドソンを、「バイク」というカテゴリーから「2輪車」という大きなカテゴリーに広げて、自転車にデザインを移植することで、ハーレーダビッドソンのデザインを好む人たちの心を動かすことができる
この仮説をもとに、抽象化すると
コアなファンを持つ商品のカテゴリーをさらに広げて、その中で同じテイストやデザインの商品を作ると、心を動かすことができる
という「企画のヒント」が生まれるというわけです。
では実際に、上記の「企画のヒント」を使って、別の企画を考えてみると…
手であおぐ扇子やうちわのカテゴリーを広げ、「風を起こす」という大きなカテゴリーで捉えた場合、扇子やうちわの中で昔から人気があるデザインを扇風機のデザインに移植すれば、シンプルな機能だけを持つ扇風機が売れ筋商品になる
という具合に、新たな企画を生み出すことができます。
まとめ
今回は、
- 企画を考えるときのコツ
- 企画力を鍛える方法
についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、もう一度「企画力を鍛える方法」をおさらいしておきましょう。
企画力を鍛える方法 4つのステップ
- 「人の心が動くときは、どのようなときか?」を、思いつく限りリストアップする
- 適切な質問を投げかけることによって、自分が心を動かされた出来事を思い出す
- 自分が心を動かされた出来事を掘り下げて、「心を動かされたポイント」を探る
- 「心を動かされたポイント」をもとに、自分なりの仮説を立て、それを抽象化する
今回ご紹介した内容は、私がこれまで数多くの企画を考案し、実行に移し、失敗や成功を繰り返しながら辿り着いた「ひとつの答え」にすぎません。
その他にも、いろんなコツや方法があるかもしれませんので、ぜひ「企画を考え、実行し、検証する」という経験を積み重ねることによって、自分なりの企画を考えるコツや、企画力を鍛える方法を見つけていただければと思います。
それでは最後に、「いい企画を立てるコツ」をもうひとつご紹介いたしましょう。
「なぜ企画を立てるのか」というと、人を喜ばせたいから。
そこを原動力にして企画を立てる心の習慣が大切です。
なぜなら、たんに「仕事で企画を立てなければいけないから」という場合と、「誰かを喜ばせたいから」という発想で立てるときとでは、明らかに企画の出来が違ってくるからです。
出典:斎藤孝(2011)『斎藤孝の企画塾 これでアイデアがドンドン浮かぶ!』株式会社筑摩書房.
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました (^.^)
以下、この記事を読んでくださった方へ「オススメの記事」をピックアップしましたので、お時間がございましたらぜひご一読くださいませ。