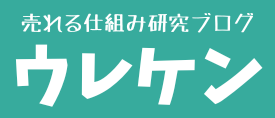「顧客満足度を上げるシンプルな方法は?」
「顧客満足度を向上させる取り組みとは?」
「顧客満足度を調査する方法が知りたい」
というあなたに、今回は
- 顧客満足度の向上につながる3つの取り組み
- 顧客満足度を上げるための3つの方法
- 顧客満足度の重要性や、満足度調査のやり方
- 顧客満足度と従業員満足度の関係性
について解説いたします。
※ここで言う「取り組み」とは、「どうするか」「どうすべきか」といった「方向性を示す行動」を表しており、方法とは「実施すべき具体策」を意味しています。
お客様はしばしば自分勝手でわがままな一面を持っていますから、すべてのお客様にご満足いただくことは簡単ではありません。
ブログやSNSを通じて誰でも簡単に情報を発信できるようになった今日、良い情報だけでなく、自社にとって都合の悪い情報も一瞬で拡散されてしまいますから、今まで以上に顧客満足を高める取り組みや施策を継続的に行う必要があります。
加えて、顧客満足度を高めることが企業にとって必要であることは、ビジネスパーソンであれば何となく理解していると思いますが、顧客満足度がどれほど重要で、具体的にどうやって調査すればいいのか?を正しく理解している人はどれくらいいるでしょうか。
「情報化社会における、顧客満足度を向上するための方法論」
と言えば、少々言い過ぎになるかもしれませんが、今後ますます加速度的にインターネット上のやりとりが増えることを考えると、顧客満足度の向上につながる取り組みや施策を置き去りにしたまま、安心してビジネス活動を継続することはできません。
それでは早速、顧客満足度の向上につながる取り組みや方法、重要性や調査のやり方などを、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
顧客満足度向上の取り組み
顧客満足度向上の取り組みとは、一体どのようなものか?
顧客満足度の向上につながる取り組みを明らかにするために、まずは顧客満足度を下げるシチュエーションを想像してみましょう。
例えば、あなたが、
「このメーカーの商品を2度と買うことはない」
「このサービスには心底がっかりさせられた…」
「比較検討していた別の商品にすべきだった…」
と感じた商品やサービス、あるいは会社やお店を思い出してください。(嫌なことを思い出させて誠に恐縮です…。)
いかがですか?思い出せましたか?
では、あらためて、あの時どうなっていれば顧客満足度の向上につながったと思いますか?
その答えの中に、顧客満足度向上につながる取り組みのヒントが隠されています。
おそらく、以下にご紹介する「取り組み」がなされていたなら、少なからずあなたの顧客満足度は下がることなく、場合によっては上がっていたかもしれません。
顧客満足度向上につながる3つの取り組み
- 超長期的な視点で考える
- 品質を何よりも優先する
- 顧客の気持ちに寄り添う
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
超長期的な視点で考える
顧客満足度の向上につながる取り組み、ひとつ目は「超長期的な視点で考える」です。
今の時代、長期的な視点で考えるのは当たり前であり、人生100年時代と呼ばれる今日においては、「超」長期的な視点でものごとを捉え直す必要があります。
と言っても、難しく考える必要はありません。
例えば、製品を無料で修理・交換する保証期間を1年間から2年間に変更する。
あるいは、競合他社の保証期間をリサーチして、業界最長の保証期間を実現する。
今まで当たり前とされてきた保証期間を見直すことによって、お客様に安心をお届けできるだけでなく、製品を製造する企業も「より壊れにくい商品」を考えるようになりますから、製品の耐久性を向上することにもつながります。
保証期間の他にも、
- 保有ポイントの有効期限を延長する
- 割引クーポンや金券の有効期間を延ばす
など、まずはできることから始めてみてはいかがでしょうか。
品質を何よりも優先する
顧客満足度の向上につながる取り組み、2つ目は「品質を何よりも優先する」です。
前項でもお伝えした通り、人間の寿命は確実に伸びていますから、人は自然と「長く使える商品」を選ぶようになり、「長く使うのなら少々お値段が高くても良いものを」と考える人が増えて、今まで以上に品質にこだわるようになることが予想されます。
加えて、世界が抱える大きな問題として、環境破壊や資源の枯渇などがあり、今後はよりいっそう環境に与える負荷を減らそうとする動きが活発化するでしょう。
そうなると、ますます消費者の品質へのこだわりが見られるようになり、粗悪な商品や環境に負荷を与える商品は少しずつ市場から淘汰され、逆に、確かな品質と、人や環境に優しい商品が多くの消費者に選ばれるようになります。
そういう意味においては、商品の品質だけでなく、リサイクル素材を使った商品やフェアトレード認証製品のような「それを選ぶことに意味がある商品」にもっと目を向ける必要がありそうです。
顧客の気持ちに寄り添う
顧客満足度向上につながる取り組み、3つ目は「顧客の気持ちに寄り添う」です。
簡単そうに見えますが、これが意外と難しい。
商品の売買や商取引など、あらゆるものがインターネットを通じて行われるようになった今日、対面営業や対面販売の機会はますます失われ、電話でお客様と直接お話しすることも少なくなりました。
目の前にいる人を相手に商品を説明しているときは、表情や声のトーン、話し方や仕草、身なりや持ち物などから、お客様が求めているものや達成したいことを予測したり、お客様の性格や気分を少なからず感じ取ることができます。
しかし、自社のネットショップを訪れているお客様に関しては、商品を閲覧したり、商品をカートに入れるなど、お客様が何かしらの行動を起こさない限り、何も知ることができません。
そのため、今まで以上に顧客の気持ちに寄り添ったホームページやランディングページ、ブログやメール、チラシやパンフレットの制作が求められるでしょう。


顧客満足度を上げる方法
前項でお伝えした「顧客満足度の向上につながる3つの取り組み」を踏まえた上で、この項では、顧客満足度を上げる方法を3つご紹介いたします。
顧客満足度を上げる方法
- 日本一のわかりやすさを追及し続ける
- 日本一の顧客対応を考え、浸透させる
- 日本一の安心・安全・安定を構築する
「言われてみれば当たり前」
と思われるかもしれませんが、世の中の大事なことは、往々にして単純でシンプルです。
しかしながら、この単純かつシンプルな方法を、高いレベルで実行できている企業が少ない…そう感じるのは私だけではないと思います。
だからこそ、今あらためてこの3つの方法に真正面から向き合い、
「自分たちに何ができるか?」
という問いを自らに投げかけて、具体策を考え、できることから少しずつ実行に移すのです。
結果を目にするまでは少し時間がかかるかもしれませんが、お客様の反応が今までとはまったく異なるものに変わることをお約束いたします。
それではひとつずつ見ていきましょう。
わかりやすさを追及し続ける
顧客満足度を上げる方法、ひとつ目は「日本一のわかりやすさを追及し続ける」です。
以前に比べると、いくらかマシになったとはいえ、依然として世の中は「わかりにくいもの」が結構あります。
私が最近「この説明、わかりにくいなぁ…」と感じたものは、
- マイナポイントの申請方法
- e-taxで確定申告を行う方法
でしょうか。(単に私の知識不足かもしれませんが…)
とにかく、自社の商品やサービスを、あらためて消費者の目線から眺めてみると、わかりにくい箇所がいくつか見つかるはずです。
- 特徴や機能、他社との違い
- 使い方やメンテナンス方法
- お問い合わせ先や連絡先
- 会員登録や解除する方法
- できることやできないこと
- 向いている人や不向きな人
など、他社のそれと比較しながら定期的にチェックしてみましょう。
チェックするときのポイントは、「誰にとってわかりやすくしたいのか?」を明らかにすること。
商品やサービスを開発した当初に定めていたターゲットと、今現在、自社の商品やサービスを利用しているお客様が乖離している場合は、ターゲットを再設定した上で改善策を考えてみましょう。
顧客対応を考え、浸透させる
顧客満足度を上げる方法、2つ目は「日本一の顧客対応を考え、浸透させる」です。
ここで言う「顧客対応」とは、対面や電話、チャットを通じて行う対応だけに限定したものではありません。
お客様が目にするものをはじめ、触れるもの、操作するものなど、五感を通じて自社の商品やサービスを知り得るすべてのものが、顧客対応となります。
ターゲットとする顧客にとって最適なデザインやレイアウト、配色やBGM、形や大きさ、匂いや手触りなど、すべてにおいて
- 知りたいことが、すぐに見つかるようにするにはどうすればいいか?
- ストレスがなく、安心してお使いいただくにはどうすればいいか?
- スピーディーに、問題が解決できるようにするにはどうすればいいか?
を考え、トライアンドエラーを繰り返しながら、より良い顧客対応を模索するとともに、確実に浸透させるのです。
そうすることによって、気がつけば競合他社との差はグングン広がり、
「他の誰でもなく、あなたにこの仕事を依頼したい」
「自分には、この商品でなければ、まったく意味がない」
「御社のサービスに全幅の信頼を寄せている」
と言われるまでに成長して、顧客満足度を飛躍的に上げることができるでしょう。
安心・安全・安定を構築する
顧客満足度を上げる方法、3つ目は「日本一の安心・安全・安定を構築する」です。
顧客の信頼を最も損なう出来事といえば、商品やサービスを利用していることで不利益を被ったり、被害が生じるなど「期待を大きく裏切られること」です。
では、顧客満足度が最も向上するときは、一体どのようなときか?
それは、
- 期待を大きく上回ったとき
- 危機的状況を救われたとき
この2つです。
日本一の「安全・安心・安定」を構築すると言うことは、見た目に大きなインパクトを与えるわけではありませんが、いざと言うときに危機的状況を救ってくれます。
お客様に、
「この商品に決めて正解だった」
「このサービスにして良かった」
「御社に任せて本当に良かった」
と心から感じていただけたとき、顧客満足度は急上昇し、商品やサービス、会社やお店に対して揺るぎない信頼が生まれます。
上記のことからも、今ある商品やサービスを、ほんの少しでも「安心できる、安全に使える、安定している」ものに改善し続けることが、顧客満足度の向上には欠かせません。
顧客満足度の重要性
顧客満足度の重要性とは何か?
消費者が商品やサービスを選ぶとき、最も重視しているのは価格と品質でしょう。
その他にもデザインや大きさ、スピードや手軽さ、機能性や保証の手厚さなど、様々な要素を考慮して、自分にとって最適な商品やサービスを選びます。
そして、一定の割合で
「最終的にはお客様の評価やレビューで決定する」
「数値化された顧客満足度があれば、大いに参考にする」
という方もいらっしゃいます。
顧客満足度とは、言わば、顧客が評価した「商品やサービスの成績表」に他なりません。
すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、「成績表」ということは、価格や品質、デザインや大きさ、スピードや手軽さ、機能性や保証の手厚さなど、それらすべてが含まれていて、しかも、評価しているのは商品やサービスを実際に利用している「顧客」です。
そういう意味においても、商品やサービスを選ぶ上で、顧客満足度は極めて重要だと言えるでしょう。
さらに、顧客満足度が高い商品やサービスは、
- 自然に口コミや紹介を誘発させて、新規客をつれてくる
- リピーターを増やし、安定的な売上をもたらしてくれる
- 知名度や評判が上がるにつれて、ブランド力が向上する
という、とてつもなく大きなメリットを手にすることができます。
上記のことからも、顧客満足度の重要性がお分かりいただけるのではないでしょうか。
顧客満足度調査のやり方
顧客満足度調査のやり方を解説いたします。
顧客満足度の運用方法にもよりますが、顧客満足度を数値化して自社メディア(ホームページやブログ、チラシやパンフレット)に掲載したり、社内で情報共有する程度であれば、お客様へのアンケート調査がオススメです。
その他にも、対面型のインタビューや電話調査などがありますが、費用対効果を考えると、アンケート調査一択で問題ないでしょう。
顧客満足度調査のやり方は「顧客アンケート」に委ねるとして、次に考えるべきは
「どのような指標で顧客満足度を把握するのか?」
ということです。
これに関しても、顧客満足度に関連する指標はいくつかありますが、先に申し上げた自社メディアへの掲載や社内での情報共有が主な目的であれば、「顧客満足度」と「顧客ロイヤルティ」を測定することができれば問題ありません。
ちなみに、顧客ロイヤルティとは、顧客が特定の商品やサービスに対して感じる「信頼」や「愛着」のことを指します。
つまり、アンケート調査によって、顧客の「満足度」と「信頼度」を把握するのです。
それでは、まずはじめに顧客満足度の測定方法を解説します。
何となくイメージできる方も多いかとは思いますが、簡単にご説明すると、
顧客満足度の測り方
- 「たいへん満足している」「そこそこ満足している」「あまり満足していない」など、段階的に満足度を示す回答をあらかじめ提示する。(5段階くらい)
- 「価格」「品質」「デザイン」「機能性」など、質問項目を設ける。
- それぞれの質問項目に対して、該当する満足度にチェックしてもらい、最後に回答者の平均値を出す。
となります。
次に、顧客ロイヤルティの測定方法を解説します。
なお、顧客ロイヤルティに関しては、NPS(Net Promoter Score:ネット・プロモーター・スコア)という測定方法を使って、商品やサービスの「オススメ度」を計測します。
顧客ロイヤルティの測り方
- 「あなたはこの商品を家族や友人、職場の同僚にどの程度おすすめしたいですか?」という趣旨の質問を投げかけて、回答者に0~10点で点数を付けてもらう。
- 点数に応じて、回答者を「9~10点の場合→推奨者」「7~8点の場合 →中立者」「0~6点の場合 →批判者」に分ける。
- 「回答者における推奨者の割合(%)」と「回答者における批判者の割合(%)」を出して、「NPS=(推奨者の割合)ー(批判者の割合)」の計算式で数値化する。
例)推奨者が65%、批判者が15%だった場合、NPSの数値は「+50」となります。
顧客満足度や顧客ロイヤルティを数値化したところで、詰まるところ、その数値が
- 業界の平均値に比べて高いのか?それとも低いのか?
- 過去の数値に比べて上がっているのか?下がっているのか?
がわからなければ意味がありません
そのため、顧客満足度や顧客ロイヤルティを数値化する際は、可能であれば業界の平均値を調べたり、あるいは、定期的かつ継続的に計測して、前回よりも今回、今回よりも次回の数値が上昇するように、具体的な取り組みや施策を実行することが重要です。
その結果、
「この取り組みは上昇率が高い」
「この施策は効果が低い」
など、それぞれの取り組みや施策の費用対効果を把握することによって、より効率的に、顧客満足度を高める活動にフォーカスすることが可能となります。
顧客満足度と従業員満足度の関係性
顧客満足度(CS:Customer Satisfaction)と、従業員満足度(ES:Empleyee Satisfaction)との間には密接な関係があることをご存知でしょうか。
先に顧客満足度の重要性について述べた通り、顧客満足度を上げることは、会社の業績アップには欠かせません。
業績がアップすると、一般的には従業員の給与や賞与に反映され、場合によっては職場環境が改善されたり、福利厚生が充実するなど、結果として従業員満足度が高まります。
そして、従業員満足度が高まれば、優秀な人材が会社に定着するようになり、自然とお客様に対する「サービスの質」が向上し、顧客満足度の向上につながっていきます。
この好循環を生み出すことができれば、企業の成長はもとより、短命と言われるこの時代に、長寿企業の仲間入りができるかもしれません。
反対に、どんなに優れた設備を有していても、どんなに優れたシステムを導入しても、顧客満足度を高める視点を持つことなくビジネス活動を続けていると、いつしか業績が頭打ちになって、従業員満足度を高めることも叶わなくなり、それが原因で顧客満足度を下げてしまいます。
そんな悪循環に陥らないように、顧客満足度と従業員満足度の関係性を正しく理解して、両方の満足度を高めるための取り組みや施策を実行することが大切です。
まとめ
今回は
- 顧客満足度の向上につながる取り組み
- 顧客満足度を上げるための3つの方法
- 顧客満足度の重要性や、調査のやり方
- 顧客満足度と従業員満足度の関係性
について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
忘れないように、もう一度「顧客満足度向上の取り組み」「顧客満足度を上げるには」をおさらいしておきましょう。
顧客満足度向上につながる3つの取り組み
- 超長期的な視点で考える
- 品質を何よりも優先する
- 顧客の気持ちに寄り添う
顧客満足度を上げる方法
- 日本一のわかりやすさを追及し続ける
- 日本一の顧客対応を考え、浸透させる
- 日本一の安心・安全・安定を構築する
顧客満足度を高めるコツがあるとすれば、私は迷わず
「自社の商品やサービスを必要とする人に販売すること」
と言うでしょう。
では、自社の商品やサービスを必要としている人を顧客にするためにはどうすればいいのか?
それは、詰まるところ、
「できることと、できないことをはっきり伝えること」
ではないでしょうか。
自社のサービスの範囲を超える依頼を受けたり、売上欲しさに自社では対応に困る注文を受けたり、キャパシティを超えている状態で安易に仕事を受けてしまうと、トラブルやミスを招くことになり、結果として、顧客満足度を上げるどころか、顧客満足度を著しく下げることになりかねません。
注文を受ける前に、「できないこと」をちゃんと伝えておけば、お客様に無理難題を突きつけられることもありませんから、余計な時間を使うことなく、自社の商品やサービスに納得していただけるお客様に貴重な時間を費やすことができます。
トヨタ自動車株式会社の豊田章男社長が、
『「決断」とは「断ずる」(やめる)ことを「決める」ことだ』
とおっしゃっているように、「やらないこと」をしっかり決めて、「やること」「やれること」に全力を注ぐことが、顧客満足度向上の王道であり、最短ルートかもしれませんね。
最後にもうひとつ。
「アンケートの作成や実施、回収や集計、分析や活用をもっと効率的に行いたい」
という方に、
- Webアンケート作成サービス
- メール配信システム
をご紹介いたします。
Webアンケート作成サービスとは、専用テンプレートを使ったアンケートフォームの作成をはじめ、アンケートの実施や集計を包括的に行うことができるサービスです。
- アンケートフォームの作成
- 自動返信メールの設定
- 送信確認・完了画面の設定
- アンケート結果の集計
- 回答データの保存・ダウンロード
など、Webアンケートを実施する上で必要な機能が全て備わっているので、お客様アンケートをはじめ、社内アンケートや顧客満足度調査、プレゼント応募用アンケートなど様々なアンケートに活用できます。
- アンケートフォーム無料作成おすすめサービス5選
- アンケートフォーム無料・有料プランを徹底比較
メール配信システムとは、登録したメールアドレスに対して一斉にメールを配信できる便利なサービスで、Webアンケートを実施する際に重宝します。
- HTMLメールの作成
- メールの開封率を測定
- 本文内のURLクリック率の測定
- ターゲット別の配信
- 配信日時を指定
- 本文中に送信先の社名を差し込む
など、メール配信に必要な機能がすべて備わっているので、お客さまアンケートだけでなく、
- メルマガ配信やステップメール配信
- 新商品や新サービスのご案内
- キャンペーンやセールのお知らせ
- 値上げや値下げのお知らせ
- 商品やサービス内容の変更通知
- お詫びやメンテナンスのお知らせ
その他の重要なお知らせなどを行う際にたいへん便利です。
- メール配信システム比較!5社の特徴と活用法
- メール配信システム 目的別おすすめランキング
いずれのサービスも、無料プランや無料トライアル期間を設けているので、少しでも気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
なお、
「実店舗にご来店いただいたお客様に、その場でアンケートを実施したい」
という方は、以下の記事にて自由にお使いいただける「来店アンケートテンプレート」をご用意しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
ということで、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき、ほんとうにありがとうございました (^.^)